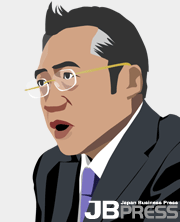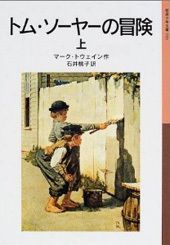米国と中国の水掛け論
問題をドルに対する人民元の過小評価(ペッグ)と、その他通貨に対するドル安とに分けて考えてみよう。
ドルペッグ制についての中国の主張は、「米国の超低金利政策が大規模なドルキャリートレードを促し、資産価格に世界規模で影響を及ぼしている。巨額の財政赤字は、ドルの更なる減価や米国債の減価によって、中国の保有資産を毀損するリスクにつながる。金融・財政政策運営を健全化させてドル価値の安定化を図るべき」というもの。
一方、米国の言い分は、「金融の超緩和や財政の拡大は未曾有の経済の落ち込みに対応した政策で、やむを得ないもの。金融緩和を早期に解除し財政を引き締めれば、米国経済は再度悪化し、世界経済の回復を遅らせることになる。問題は、人民元をドルにペッグさせ、経済ファンダメンタルズを為替レートに反映させない中国の姿勢だ」というもの。
こうした水掛け論を国際社会の目にさらすわけにはいかず、両国は為替問題を首脳会談のアジェンダから排除したものと思われる。
しかし、中国は、ドルペッグを続けることの弊害も知らないわけではない。国内でのインフレ懸念の台頭と国際社会におけるリピュテ-ションの悪化である。外圧による政策変更を嫌う中国の体質を考えると、世界経済の立ち直りにより輸出の回復がより確かなものになった2010年のどこかの段階で、自主的に緩やかな人民元高への誘導を再開するものと考えられる。その時期はそう遠い先ではない。
ドル安がもたらす弊害
米国の中国に対する「人民元を低位に据え置いている」という不満は、そのまま他国の米国に対する不満になる。ドルの実効為替レートは歴史的低水準に近づいており、中期的なインフレやドル減価への備えとして、投資家が資産分散先として金を選好する動きも目立ってきている。
また、各国中央銀行が外貨準備をドルから他通貨(ユーロやSDR)や金に分散する動きも続いている。ハーバード大学のフェルドシュタイン教授は12月10日のフィナンシャル・タイムズ紙に寄稿し、「ドルは、多くの国にとっての単独の準備通貨としての位置づけから、投資通貨という役割に変質した」と指摘した。
一方、世界銀行のゼーリック総裁は「ケインズを重視するあまり、フリードマン(マネタリスト)を軽視してはならない」という表現で、財政拡張と同時に行われているマネー拡張(超金融緩和)がもたらす資産バブルの萌芽に警鐘を鳴らしている。
米国の低金利とドル安は各国の輸出抑制につながるのみならず、様々なルートを通して、アジアをはじめとする各国の資産価格に歪みをもたらし始めている。