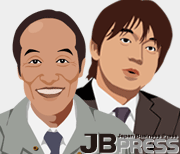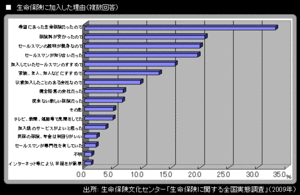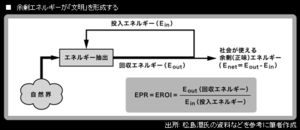自動車業界は「干天の慈雨」によって、なんとか息を吹き返しつつある。
減税&補助金で自動車業界はホッと一息? (決算発表するトヨタ自動車の一丸陽一郎副社長)〔AFPBB News〕
2008年秋の金融危機のあおりを受けて生産半減というどん底状態が半年あまり続いたが、「エコカー減税」「エコカー補助金」など政府によるインセンティブが与えられたことで、2009年度の第2四半期以降の生産は増加基調。当初計画に対しトヨタ自動車が14.8%増の155万台、ホンダが19.8%増の68万5000台としたほか、乗用車メーカー5社が上積みを見込んでいる。
しかし、まだ、予断は許されない状況だ。減税や補助金は需要の先食いに過ぎず、打ち切り後の販売低迷は想像するだに恐ろしい。CO2排出削減という中長期の技術開発の高いハードルも待ち構えている。
ただ、それ以上に気掛かりなのは、「クルマそのものの存在意義」を維持していくことができるか――ということだ。
自動車各社にとって、このところの最重要テーマは「燃費」と「低価格」の2つ。こうしたキーワードの実現には、あらゆる無駄をそぎ落とすことが不可欠になるが、目標達成のために過剰なダイエットに取り組んだ車がどれだけ魅力的に映るかは疑問だ。
理論の追求で没個性化
個性的な名車たち インパラ〔AFPBB News〕
誤解を恐れずに言えば、クルマは無駄の塊であるがゆえに、多くの人々の心を捉え、興味を惹きつけてきた。
例えば公道を走行するのには不必要な数百馬力もの高出力、1950年代のアメ車(米国車)のテールフィンのような大げさな装飾、太くて大きなタイヤ・・・。「燃費」という発想はなく、ガソリンをまいているようなクルマばかりだったが、「アメリカングラフィティ」(1973年米国、ジョージ・ルーカス監督)のインパラも「ブリット」(1968年米国、ピーター・イェーツ監督)のマスタングも文句なしにカッコよかった。
試験設備は現在ほど発展していなかったため「空気抵抗は流線型の方が少ないはず」といったイメージで、実証の裏付けなく車体がデザインされることが多かった。当時もそれなりの流行はあったが、開発者の熱い思いが先行することがほとんどだったため車種それぞれのデザインは非常に個性的だった。