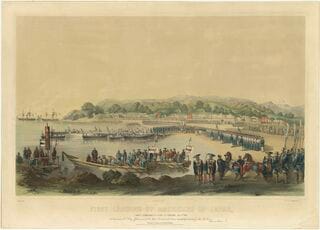中南米のラテン系やアフロ系、先住民族、その混血系の中にしばらく身を置くと、習慣や民族の本質的な何かが違うせいか、異種の中にいるという軽い緊張感と朧(おぼろ)な違和感にみまわれ、虞(おそ)れというか、どこか心の底がしずまらずエネルギーが消耗されるものだ。
そんな中で旅をしていると、日本の閉塞感や建前重視の社会に合わずに日本を飛び出した人間でも、時おり祖国が恋しくなることがある。
米が無性に食べたくなったり、日本人特有の会話のニュアンスや、相手を思いやり、どこか遠慮がちで、礼儀正しく、奥ゆかしいという美しい日本人気質に無性に触れたくなるものだ。
そんな時、日本人宿は郷愁を満たしてくれる格好の憩い場となる。宿に着けば、「お疲れさま」とか、中には初めて来たのに「お帰りなさい」なんて泣かせるせりふで迎えてくれるところもある。
過去を吐露し始めた2人の日本人
灼熱の空気が苦しいほど熱い、赤道近くの夏のある日。メキシコのカンクンの長距離バスターミナルに到着すると、私は、ある日本人宿を目指した。バス停から僅か1キロメートルの距離をリュックを背負って歩いただけで、シャツが絞れるほど汗だくになり、不快に肌に張りつく。宿は閑静な住宅街の一角にあった。個室はあいにくの満室、空いているのはドミトリーのみというが、再び炎天下での宿探しもしんどいので、今晩はここで我慢することにした。
夕方、宿のキッチンでビールを飲み、久しぶりにNHKニュースを見ると、相変わらずの殺人、汚職の話題ばかり。しかし、自分自身が今、日本の社会に参加していないせいか、なにか遠くの巷間を見ているような感じがする。
ぼんやりテレビを見ていると、背後から背の高い角刈りの40代後半という男と、背の低い礼儀正しい20代後半の男がキッチンに入ってきた。ちょうど腹も空いてきたので近所のうまいと評判の安食堂にて、情報交換がてら共に晩餐をすることになった。
角刈りの男、Tはメキシコの北の地域でプレス加工の技術指導監督をボランティアでしているという。背の低い男、Yは大阪で半導体の営業をしており、休暇でメキシコにきたという。カリブ海で採れたばかりの海鮮に舌鼓を打ちながらテキーラが胃袋に滲みると、各々の過去を吐露し始めた。