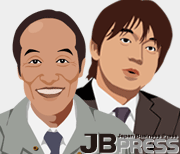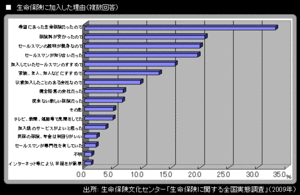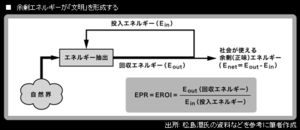熟練工を頂点に据えるトヨタ流人事
愛知県田原市のトヨタ自動車の田原工場。最高級車レクサスを生産するこの工場では、「匠」(たくみ)と呼ばれる熟練工の技と最先端技術を数多く織り込んだ独自の塗装ラインを採用している。
複雑な凹凸を持つドアの内部から普段は目に触れることのないエンジンルームまで、外板と同じように熟練者が丁寧に塗装を施すほか、工程の最後には匠が手作業で「水研ぎ」をする。この流水をかけながら専用の機械と耐水ペーパーで表面を繰り返し磨いていく手の込んだ作業で、サイドやフロントの平面部は目に見えないわずかな部分まで滑らかになり、漆をかけたようなつやが出る。量産の低価格車には決して見ることのできない光沢だ。
残念ながら昨年来の世界同時不況の影響で、この宝石のようなクルマの売れ行きは芳しくない。だが、この工場には金色の刺繍が入った作業帽を被ることを許された「匠」を頂点とする、技術のヒエラルキーが存在している。
熟練技能者にはシニアが多い。放っておけば彼らの持つ高度な技能は徐々に失われてしまう。彼らの技能が若手に引き継がれていけばいいのだが、熟練者と若手との差が大きすぎる。熟練者は「技術は盗むもの」と育てられてきたから若手に教えることに消極的だし、若手も根気が続かない。
技術の伝承は熟練者と若手がコミュニケーションを取れなければ成り立たない。勘やコツを習得するために「実技課題」を若手に与え、熟練者がマンツーマンで指導する。若手は先輩に質問を繰り返して技能の習得に励み、定期的に実施される「技能テスト」に挑む。クリアすれば昇級が約束される。いつか最高位の匠になれば、役員クラスの待遇が待っている。
つまり「匠制度」は、カンコツを極めた熟練工を頂点に据えることで技能の継承や従業員のやる気を引き出すという、トヨタ流の人事政策なのだ。
熟年者が蓄積した技術を次世代に伝えられるか?
宝石のように輝くレクサス〔AFPBB News〕
もちろんトヨタの匠制度のような取り組みがすべての現場で実施されているわけではないし、匠制度が必ずしもうまく回っているわけではない。カンコツは個人個人の能力に左右される部分がきわめて大きいからだ。
ならば、カンコツを持つ人たちを大事にするのも一案かもしれない。若手が一朝一夕には培えない経験やノウハウを持っている人たちの定年年齢を延長する。あるいは再雇用する。豊富な経験と専門知識を持つシニアは即戦力になるし、若手を一から育て上げる時間やコストを節減できるから経営にも寄与するだろう。
現場の熟練者が持つ技能やノウハウは日本を支えてきた。2007年問題で定年退職者が増加し、人口減も進む中、熟年者が蓄積した技術を次の世代に伝えきれているだろうか。終身雇用や年功序列の弊害を重視して、効率性を追求するあまり、大切な日本の財産まで切り捨ててはいないだろうか。
日本の国際競争力を保つためにも、カンコツを生かす道を考えなくてはならない。