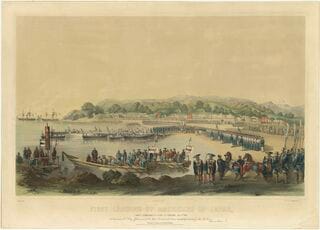「Never say never」という箴言(しんげん)がある。「絶対ないとは言うな」の意だが、台湾が「中国」に取り込まれること、つまり「中台統一」の実現にもこの言葉が当てはまる。
中台統一はこれまで「限りなく不可能に近い」と考えられてきた。民主体制下にある台湾の人々が「共産党の独裁下にあり言論の自由もない中国」との「統一」など、望むはずがないからだ。
よって、もし「統一」があり得るとするなら、それは中国による「武力統一」ということになるのだが、その場合、中国に十分な揚陸作戦能力がないこと、台湾空域で台湾側が航空優勢を確保していること、さらに「台湾関係法」に基づき、米国が台湾の安全保障にコミットしていることを勘案すれば、中国による「武力統一」も、限りなく不可能に近いのが現実だと考えられてきた。
だが、経済面に限って言えば、中国と台湾は急速に緊密な関係を築きつつある。経済面での接近が政治面にも波及していくことは十分に予測できる。仮に中台統一が実現されたら、東アジアの安全保障環境は大きな変化に見舞われ、日本も対応を迫られることになる。
今回は、前篇と後篇に分けて、中台統一の現実性と日本への影響を考えてみたい。前篇では、中台統一を巡る中国の思惑を明らかにする。後篇では、中台統一が実現された場合、東アジアの安全保障環境がどのように変化するのか、そして日本がどのような対応を迫られるのかを検討する。
経済面で大陸への依存度を高める台湾
2000年以降、中国と台湾は経済関係を急速に強化している。李登輝総統時代の1990年代は、台湾は大陸との経済関係において「戒急用忍」政策を取り、大陸への依存度が過度に高まることを警戒していた。しかし、2000年に台湾で陳水扁政権が誕生すると、アジア通貨危機以来の不況下にあった台湾経済を活性化させるために、大陸への積極的な投資を奨励する「積極開放、有効管理」政策を取った。
その結果、台湾は、貿易における大陸への依存度が2007年に40%を超えるまでになってしまった。もちろん中国が最大の貿易相手国であり、大陸に台湾のビジネスマンが100万人以上駐在するという事態となったのだ。
陳水扁政権は、2006年には政策を「積極管理、有効開放」に切り替えたが、台湾経済の大陸依存への流れを変えることはできなくなってしまっていた。
2008年3月の総統選挙で馬英九が「中台共同市場」を選挙公約に掲げ、地すべり的勝利を収めた背景には、こうした経済的な「中台一体化」という人心にとって抗し難い現実があった。
その馬英九政権の成立から早くも1年が経過したが、中台の懸案であった「三通(通商、通航、通郵)」が2008年末に実現し、当初週末限定のチャーター便だけだったのが、2009年7月から週に270便の航空定期便が両岸を結ぶこととなった。