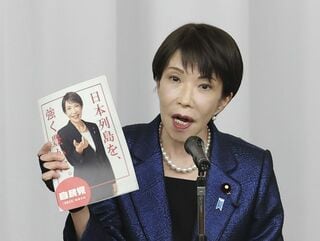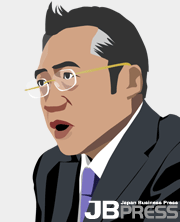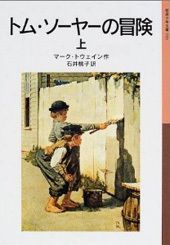市場は完璧ではないが、監督機関はなおさら完璧でない(投資家ジョージ・ソロス氏、資料写真)〔AFPBB News〕
残り0文字
一方、米著名投資家のジョージ・ソロス氏は、ホワイトハウスの金融規制改革案発表に先立って6月17日のFT紙に寄稿。「規制緩和が今回の危機の伏線となったことは確かだが、その揺り戻しが、監督強化の行き過ぎとなってはならない。市場は完璧ではないが、監督機関はなおさら完璧ではない。彼らも人間であり、同時に官僚であるため政治的影響は排除できない。それゆえ、規制は最小限にとどめなくてはならない」と、過度な規制に振り子が振れ過ぎることに警鐘を鳴らした。
金融規制改革は米国のみならず欧州でも議論が始まっており、欧州連合(EU)レベルでの銀行監督機関の設置や、主要銀行や国境を跨いで活動する銀行をいかに監督していくかが議論されている。米欧におけるこれら議論で重要なポイントは、(1)IMFやG20を通じた各国協調した金融監督指針と、(2)各国各地域内で統制の取れた金融監督体制との両立だ。
今回の米国の改革案は、多くの金融監督機関の並存を是正し、金融システム全体の監督をFRBに担わせるというものだ。システミックリスク(連鎖破綻)を引き起こし得る巨大金融機関であるにもかかわらず、連邦レベルの監督がなされていなかったアメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)等の保険会社も、今後はFRBの監督下に置かれる。上述の(2)の目的に即してよく練られている印象であり、今後他国での議論にも影響を与えていく可能性がある。
ソロス氏が危惧する「過度な規制」かどうかは、今後の議会での議論の成り行きや監督当局の方針を見極めなければならないが、銀行に「アメ」(流動性供給、資本注入)を与えることで機能回復を優先させてきた段階から、二度と同じ過ちを繰り返さないための「ムチ」(規制監督)の段階に進んだことは確かだと言えよう。
黒字国と赤字国の不均衡見直しを
金融危機の原因は「規制の失敗」(グリーンスパン元FRB議長)〔AFPBB News〕
「米国主導の国際金融秩序」を伏線とし、「規制の失敗」を直接の原因とする今回の金融危機の背景には、さらに大きな、そして最も解決困難な問題が存在する。日本、中国、ドイツを代表格とする経常黒字国と、米国を筆頭とする経常赤字国との間に存在する不均衡だ。
多くの識者が、現在は、「アジアがモノを作り、アメリカ人が消費する従来のグローバル経済モデルが崩壊した歴史的転換点」であると指摘する。
過去20年の中国を含むアジアの急成長を支え、日本やドイツも恩恵に与ってきたこうした経済モデルが、巨大な米国消費者の需要を頼りにできなくなったことで転換を迫られている。グローバルに需要が縮小した中、黒字国が供給(輸出依存)を続ける一方では、何ら解決に向かわない。米国においては、「中国は人民元を低位に据え置いて、自国の過剰供給力を輸出している」という批判は根強い。
「元安」政策で過剰供給力を輸出〔AFPBB News〕
G20金融サミットでは各国協調した応分の財政刺激が合意されたものの、あくまで緊急事態への対応であり、財政余力のある特定国の需要(中国)に永続的に依存することは不可能だ。グローバル経済の永続的な回復のために必要な処方箋は、アジアを中心とする経常黒字国における「輸出主導」から「国内消費主導」の経済モデルへの移行である。
しかし、この問題は上述の国際金融秩序のヘゲモニーや金融規制の再構築と異なり、長期の時間を必要とする。製造業にとどまらず、金融システムや家計を含む、社会構造そのものの変革が必要になり、場合によっては既得権益に固執する政治的圧力や硬直的な経済構造が足枷となることも想定される。
輸出依存の日本経済も転換点を迎えた〔AFPBB News〕
一方で、借金漬けの米国消費者が浪費を抑制し、貯蓄性向を引き上げ過剰債務を解消していくことも必要だ。その結果、黒字国の黒字、赤字国の赤字ともに縮小が始まり、グローバル経済の不均衡が改善に向かい、より安定的な成長軌道が期待できる。
世界経済「再生」に向けた新たな秩序構築の動きは、グローバル経済モデルの転換と不均衡是正に向けた取り組み努力を促すものになるのか、再び特定国の需要に安易に依存するモデルに回帰しようとするのか、新秩序を担う各国リーダーの姿勢をじっくりと見守る必要がある。