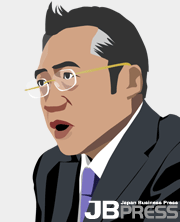『セイビング・ザ・サン』。英経済紙フィナンシャル・タイムズの元東京支局長ジリアン・テットが2004年4月に出版した著書は、当時、日本の金融関係者の間で大きな話題となった。そのタイトルには「再建途上の新生銀行(旧日本長期信用銀行)が、沈みゆく日本経済を救う存在になるかもしれない」とのメッセージが込められていた。(敬称略)
沈みゆく太陽を救えたのか?〔AFPBB News〕
1998年10月に経営破綻した旧長銀は、一時国有化を経て、2000年2月米投資ファンド・リップルウッドを中心とする投資組合に売却された。元シティバンク在日代表の八城政基を社長に迎え、新生銀行に行名を変更後は、旧来の銀行業界にはなかった新サービスを相次いで打ち出すなどして再生を図り、2004年2月、東証1部市場に再上場を果たした。
テットは日米の政財界人100人以上にインタビューを重ねたうえで、「新生銀行の歩んだ道のりは、日本の金融界に残る旧弊との格闘だった。新生銀行の成功こそが辺境の地の金融界に残る因習を打破するきっかけになる」との思いを著書に込めた。
2度目の公的資金目当てに統合交渉〔AFPBB News〕
しかし、現在の新生銀行は、日本経済を救うどころか、2度目の救済を求める状況に追い込まれている。
4月下旬、新聞各紙は、新生銀とあおぞら銀行(旧日本債券信用銀行=1998年12月破綻)が経営統合に向けた協議に入ったことを一斉に報じた。両行は、長信銀という同じルーツを持つが、新生はノンバンク事業、あおぞらは不動産金融に活路を見出すなど、目指すビジネスモデルはまったく異なっている。それが、なぜこのタイミングで統合交渉なのか。
2007年まで新生銀行に勤務していた40代の元行員は、「それぞれが単独では立ち行かなくなり、公的資金再注入を前提に経営統合したいようだ」と解説する。また、「これまでも統合話が出たことがあったが、公的資金というニンジンをぶら下げられて、株主の目の色が変わった」(金融筋)との指摘もある。
そごう破綻の引き金をひいた新生銀
再スタート直後の新生銀行は、確かに、日本の銀行界の旧弊を打ち破る勢いがあった。邦銀が課題としてきた「融資先のリスクに見合った貸出金利の設定」に挑戦し、長年にわたって守られてきた金融慣行を否定、確信犯的に業界秩序を無視した。業界内部からは、新生バッシングの声が上がる一方で、銀行本来のビジネスモデルを追求する姿勢には一定の理解もあった。
新生銀行の異端ぶりを世間に強烈に印象付けたのが、大手百貨店・そごう問題だろう。メーンバンク的存在だったにもかかわらず、同行は経営不振に陥ったそごうからの債権放棄要請をあっさり拒否し、2000年7月の破綻の引き金を引いた。
しかし、新生銀が異端者たりえたのは、旧長銀の譲渡を受ける際に獲得した「瑕疵(かし)担保条項」があったからこそだ。同行は、企業再建に汗を流すより、一定以上価値が下がった債権を、銀行の売り主だった国に返却できる契約をフル活用する道を選んだ。
新生銀の2001年3月期の連結最終利益は904億円に達し、その後も500億~600億円の利益を確保した。しかし、瑕疵担保条項の行使期限が2003年春に切れると、その後は利益が尻すぼみとなり、再上場後の経営は大きく傾いていった。