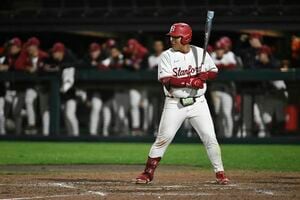「代表なら」「税金が」「結果が」――。こうした都合のいい語彙は、相手を黙らせるのにはとても便利だろう。だが、便利であることと正しいことは別だ。スポーツは国家的イベントであり、五輪は公共性が高い。だからといって選手の人格を叩き割る権利が、観衆に配分されるわけではない。
むしろ、距離が近づいたからこそ起きる副作用がある。SNSは選手の言葉や表情を“日常”として消費できる装置になった。応援もできる、共感もできる。一方で、気に入らなければ「返品」もできる――。そんな錯覚を生む。
敗者や棄権者が“尊厳を保ったまま立ち去れる場”でなければ五輪に意味がない
競技者を1人の人間ではなく、自分たちに都合のいい期待だけを叶えるための“キャラクター”として見始めた瞬間、失敗や不運は「裏切り」へと勝手に変換され、攻撃は無責任な「処罰」に転じていく。近藤選手に向けられた心ない言葉が示したのは、競技の技術論ではなく、まさにこの危険極まりない構造だ。
だからこそ、日本オリンピック委員会(JOC)が今大会で誹謗中傷対策を強化し、SNSの24時間モニタリングや、プラットフォーム事業者との連携を掲げた意味は小さくない。日本とミラノに拠点を置き、インスタグラムを運営するMetaや、LINEヤフーとも協力して、悪質な投稿の早期把握と拡散防止を図る――。これは「選手を守る」という姿勢の明確な宣言だ。
さらに、誹謗中傷を受けた当事者が相談できる窓口として、JOCと日本パラリンピック委員会(JPC)は「ホットライン」も案内している。被害の声を拾い、必要なら法務支援につなげる。スポーツ団体が“我慢しろ”ではなく、“助けを求めていい”と言い切ることは時代が変わった証拠でもある。
ただし、ここで勘違いしてはいけない。監視と通報で社会は救われない。救われるのは投稿が消えることではなく、そもそも「人を人として扱う」という最低限の倫理が共有されることだ。
言葉は冬のスポーツで例えるならば、いわば「雪」と同じなのかもしれない。ひとひらは軽い。しかし積もれば深刻なダメージにもつながる。いま、近藤選手が告げたかったのは「私は傷ついた」という事実以上に「あなたが投げた言葉は、人を壊し得る」という現実だろう。
五輪は勝者を讃える祭典であると同時に、敗者や棄権者が無念の思いを背負いつつも“尊厳を保ったまま立ち去れる場”でなければならない。近藤選手が涙をこらえながらも表に出てきた行為は、競技の外側での「勝利」だ。そこに追い打ちをかける言葉が放たれた瞬間、私たちは彼女だけでなく、スポーツそのものの価値も傷つけたことになる。守るべきは、金メダルの数だけではない。人が人であるという当たり前の線を、観衆の側が守り抜けるかどうかが問われている。切にそう思う。