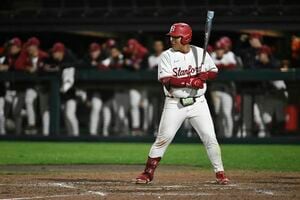近藤選手はインスタグラムで、その心ない声に反応した。「この状況の私に言う言葉?」「辞退するもしないも枠を掴み取った私が決めること」「目の前で言ってみてください」。そこには、競技者のプライドというより、踏みつけられた尊厳の悲鳴があった。
「公人だから何を言われても仕方ない」――。こうした“愚かな空気感”がもしも、この国のスポーツを取り巻いてしまっているのだとしたら真っ先に疑うべきは、その空気の方である。
近藤選手の叫び、それは弱さの表れではなく…
近藤選手はケガの前に屈し、勝敗から逃げたのでは断じてない。むしろ「逃げない」と決め、表に出て事実を伝え、悔しさも涙も引き受けた。結果がすべてだと言われる世界で、結果を出せなかった者が自分を責め、沈黙し、姿を消す――。そんな最悪の結末を、自らの意志で回避した。
だからこそ、彼女の叫びは「弱さ」ではなく、「線引き」である。ここから先は踏み込むな、と。人が人である限り、踏み込んではならない領域があるのだ、と――。
制度の整備や対策強化は、もちろん必要だ。だが最後の一線を引けるのは結局、言葉を投げる側の倫理である。
五輪は選手が試される舞台であると同時に、見る側の成熟が試される舞台でもある。近藤選手が突きつけたのは、競技の厳しさだけではない。私たちが何気なく投げた一語が、誰かの「精神の傷口」に塩を塗りたくり、広げてしまう現実である。
彼女の怒りは、いわば「防御」だった。負傷や棄権に至った経緯は、本人が誰よりも理解している。身体の痛みも、4年を積み上げてきた時間の重さも、すでに背負っている。そこへさらに事情をまるで知らないであろう第三者が“査定”のように言葉を投げつける――。この理不尽に対し、「それは違う」と境界線を引く。この一連の流れは感情の爆発ではなく、尊厳の線引きである。
 2024-25 フリースタイルスキー ビッグエアW杯 クライシュベルク大会女子予選に出場した時の近藤心音(写真:アフロ)
2024-25 フリースタイルスキー ビッグエアW杯 クライシュベルク大会女子予選に出場した時の近藤心音(写真:アフロ)
SNSの言葉が厄介なのは当事者の目の前で発せられないまま、あたかも「公共の意見」であるかのように流通してしまう点だ。しかも、それが事実に基づかず、容易に人格攻撃へ転じうる言葉であっても、時と場合によっては“正論の衣”をまといがちである。