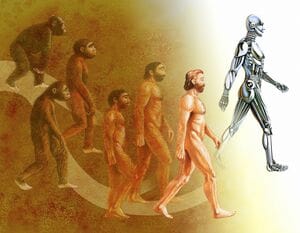伴侶を喪ったあとの生活をどう支えるか(写真:beauty-box/Shutterstock.com)
伴侶を喪ったあとの生活をどう支えるか(写真:beauty-box/Shutterstock.com)
国会で審議中の年金改革関連法案を巡ってはSNSでたびたび炎上している。自民党が一度法案から削除したのを与党と立憲民主党による修正協議で復活させた「国民年金底上げ案」もそうだが、同じくらい反発が強いのが「遺族厚生年金改正案」だ。事態を重く見た厚生労働省は、ウェブサイトに「遺族厚生年金の見直しについて」というページを開設。「遺族厚生年金の見直しについて寄せられている指摘への考え方」として誤解や拡大解釈されがちなポイントの説明を試みている。国会審議の報道では国民年金底上げ案の陰に隠れた感もあるが、この改正案、いったいどんな内容で、何が問題なのか。
(森田 聡子:フリーライター・編集者)
30歳以上の女性への遺族年金“大幅カット”で炎上
5月16日に閣議決定された法案では、遺族厚生年金の改正について次のような報道がなされている。
子のない夫婦が死別時に受け取る遺族厚生年金に、受給条件の男女差があるため、受取期間を男女とも原則5年にそろえて給付額も増やす。配慮が必要な場合は最長65歳まで受け取り可能。28年度から段階実施する(時事通信)。
遺族厚生年金とは、厚生年金に加入する会社員や公務員が亡くなった時に配偶者や子供などが受給できる年金のことだ。子供のいない夫婦の場合、現行制度では、夫に先立たれた女性は30歳以上であれば生涯にわたって遺族厚生年金が支給される。これに対し、妻を亡くした男性は55歳未満だと支給の対象にならない。
こうした男女間の格差を解消すべく、60歳未満の男女が厚生年金に加入する配偶者を亡くした場合は、「遺族年金を一律で5年間の有期給付にする」というのが今回の改正案の骨子だ。
遺族厚生年金の金額は、死亡した配偶者の生前の平均収入(平均標準報酬額)と、厚生年金への加入期間により決まる。若くして亡くなるなどして加入期間の短い人に対しては“最低保障”があり、300カ月(25年)加入したものとして計算される。
炎上のきっかけとなったのは、30歳以上の女性への遺族年金の“大幅カット”だ(20代の女性は既に5年の有期給付となっている)。