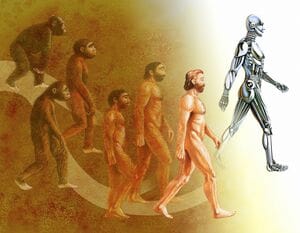年金だけで余裕のある老後を送るのは難しい(写真:Monthira/Shutterstock.com)
年金だけで余裕のある老後を送るのは難しい(写真:Monthira/Shutterstock.com)
新NISA(少額投資非課税制度)を機に株式市場には多くの若年層が流入しているが、日本の個人投資家の中心はシニア。人生100年時代とあって70代や80代の投資家も少なくない。とはいえ、今は元気でも気になるのは認知機能が低下した後はどうするのかといった将来の不安要素だ。
厚生労働省は65歳以上の認知症の有病率が2040年には14.9%に上ると推計。近年、金融機関では事前に代理人を登録しておく予約型代理人制度の導入が増え、今年2月には日本証券業協会が家族サポート証券口座のスキームを発表するなど対策の選択肢が広がっている。では、当の高齢投資家はどう考えるのか。
(森田 聡子:フリーライター・編集者)
持ち株の評価額は1200万円超、配当は年間50万円近く
来年1月に67歳になるという都内在住の男性は、「最近、自分はいつまで投資が続けられるのかを意識するようになった」と話す。
男性には子供が3人おり、2人は大学院まで進んだため教育費の負担が重く、50代はほとんど貯蓄ができなかった。定年で3000万円ほどの退職金を手にしたが、その時点で住宅ローンの残債が1000万円ほどあった。
本格的に老後資金作りに取り組んだのは60代に入ってからだ。65歳までは再雇用で働けたので生活費はその収入で賄い、60歳から公的年金等控除の範囲内に収まるように企業年金を受給し、それで高配当株を積み立て購入した。
配当も再投資に回した結果、相場環境が良かったこともあり積み立て以外も含めた持ち株の評価額は1200万円を超え、年間50万円近くの配当を受け取っている。
聞けば、男性は定年を迎えるまで、ほとんど株式投資の経験がなかったという。にもかかわらず、こんな大胆な手法に打って出られたのは、会社の先輩が同様の方法でひと財産築いた話を聞いていたからだ。