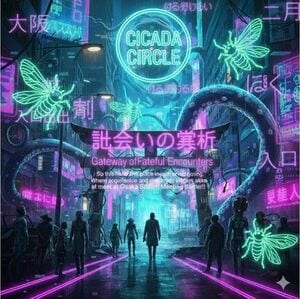1942年10月23日、日本軍の爆弾が命中し、火災を起こしたグラマン・ワイルドキャットを消火する、ガダルカナル島の海兵隊(提供:U.S. Marine Corps/AP/アフロ)
1942年10月23日、日本軍の爆弾が命中し、火災を起こしたグラマン・ワイルドキャットを消火する、ガダルカナル島の海兵隊(提供:U.S. Marine Corps/AP/アフロ)
(文:山田朗)
明治維新以降、80年間続いた大日本帝国。明治大正昭和初期と続くこの期間はまさに「戦争の時代」だった。日清戦争、日露戦争、第一次大戦、満洲事変、支那事変、そして対英米開戦まで、10年前後の間隔で大きな戦争をしていたことになる。
『日本の戦争はいかに始まったか』(新潮選書)は、それら戦役の開戦過程と当事者たちの決断を、各分野の第一人者8人が分析した講義をまとめたものだ。
そのうち、第7章「昭和天皇は戦争にどう関わっていたか」では、明治大学文学部教授の山田朗氏が最近発見された新資料に言及しながら、当時の天皇の言動を細かく分析している。ここでは、山田氏の論考に沿って、昭和天皇が実際の軍事作戦にどのように関与していたかを見てみよう。
天皇説得のための想定問答集を作成
アジア太平洋戦争が始まる前、1941年9月6日の御前会議の頃には、確たる勝算が示されないままに対米英戦争が決定されることに大きな不安を抱いた天皇は、『杉山メモ』等によれば、御前会議前日に近衛文麿首相・杉山元参謀総長・永野修身軍令部総長を呼び、「絶対に勝てるか(大声にて)」と問い質しました。
しかし、永野総長の回答は、「絶対とは申し兼ねます」というもので、天皇は確信が持てませんでした。翌日の御前会議で天皇は、明治天皇の御製「四方の海」を朗読して、統帥部の姿勢を暗に批判し、外交優先を示唆しました。天皇のこうした姿勢を憂慮した参謀本部では、服部卓四郎作戦課長が主導して高山信武課員に天皇説得のための「御下問奉答資料」(想定問答集)を作成させ、長期持久戦になれば、南方の資源を戦力化できるので有利であることなどを多くの数値を挙げて説明しました。
こうした動きが効果をあげたのか、近衛内閣の末期となった10月には天皇は次第に開戦論に傾斜し始めました。『木戸幸一日記』によれば、10月13日に天皇は木戸内大臣に宣戦布告の詔書について相談し、ドイツの単独講和を封じること、ローマ法皇庁を通じての外交チャンネルの構築の必要性について語っています。
また、東條英機陸相は、天皇を安心させようと、部下の石井秋穂中佐に戦争終末シナリオを作成させ、それは11月15日の大本営政府連絡会議で「対米英蘭蒋戦争終末促進に関する腹案」として決定されましたが、そこには天皇が木戸に語ったことが盛り込まれています。天皇の覚悟が次第に固まりつつあることがわかる。近年公開された百武三郎侍従長の『百武三郎日記』でも、11月には天皇が戦争に相当前のめりになっている旨のことが記録されています。
◎新潮社フォーサイトの関連記事
・プーチン政権「対アフリカ関与」の橋頭堡、ワグネルの知られざる利権と影響力の行方
・日本株変調に「3つの要因」、乱気流を乗り切るエンジンは「日本経済の持久力」
・技能実習制度で日本へ逃れる「カンボジア人難民」の過酷な現実