IoTの発展で必要になる人、いらなくなる人
AIとIoTの苦手な「自己意識」がキーワード
2016.10.18(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
本日の新着

大谷翔平がWBC「登板回避」、実は山本由伸の投球回数にも制限?侍ジャパンに影落とす「保険問題」という冷徹な現実
臼北 信行

なぜガウディは柱を「斜め」に建てたのか?没後100年、天才建築家の思考法をあらためて考える
寺田倉庫 G1ビルで「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」が開幕
川岸 徹

1週間装着企画:現代ビジネスパーソンに最適なデイリー・エレガンス!
オリエントスター「M45 F8 Mechanical Moon Phase Hand Winding」
土田 貴史

金急落、貴金属相場はどうなるのか ドルと円が「弱さ比べ」、通貨不安で金の上昇基調は継続か
硬貨は溶かした方が価値がある?昭和30年代発行の「鳳凰100円玉」「稲穂100円玉」の素材価値はすでに1000円超に
志田 富雄
世界の中の日本 バックナンバー

日本の土地が買われていく…高市政権は「外国人規制」に踏み込めるか?ユルユルの所有規制、現場で見てきた“惨状”
平野 秀樹

転換点を迎えた世界の移民・難民対策、高度人材の就労に寛容だったシンガポールが受け入れを絞り始めた理由
長野 光

外国人経営者の在留資格「経営・管理」の規制強化は悪手、求められる外国人の起業を促した経済活性化
山中 俊之
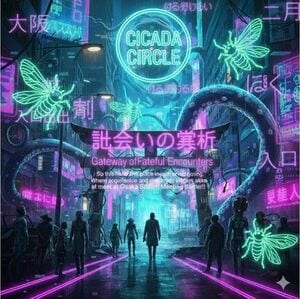
子供たちが生成AIのピンボケぶり見て大喜び、静止画・動画を簡単に作れるのに…
伊東 乾

【静かなる侵略】住民7人の離島に突如51本の電柱、岩国基地そばで進む中国資本の土地買収に住民がとった対抗策とは
平野 秀樹

長期国債大暴落、世界が恐れ始めた「高市ショック」…支持率は高いが市場の信任得られぬ首相の「責任ある積極財政」
木村 正人








