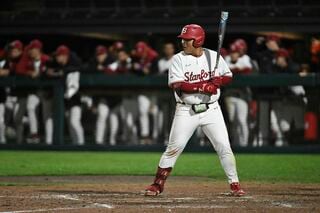ベルギー・ブリュッセルのEU本部前で風にはためく破れたEU旗(2016年3月1日撮影、資料写真)。(c)AFP/EMMANUEL DUNAND〔AFPBB News〕
イギリスが国民投票でEU(ヨーロッパ連合)からの離脱を決めたことには、多くの人が驚いただろう。事前にはかなり接戦だという予想はあったものの、常識あるイギリス人がそんな過激な手段を取るとは思わなかった。いつも正確な予想をするブックメーカーの賭け率も、9割が残留を予想していた。
ところがふたを開けると52%が離脱を選び、2年以内にイギリスはEUとの協定をすべて破棄し、各国と個別に貿易協定を結ぶことになった。準参加国のような形で残留する道もあるので、EUと100%縁が切れることは考えにくいが、ロンドンは「ヨーロッパの首都」としての地位を失い、シティは世界の金融センターではなくなるだろう。
イギリスと大陸の関係は1970年代に戻った
もともとイギリスは、大陸との仲はよくなかった。EUの出発点は1952年にできたECSC(ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体)で、イギリスは入っていない。これが1958年にEEC(ヨーロッパ経済共同体)ができ、EC(ヨーロッパ共同体)に発展したあとも、フランスのドゴール大統領はイギリスの加盟に反対した。彼の死後、1973年にイギリスはECに加盟した。
ECは1993年にマーストリヒト条約でEUになり、1999年に統一通貨「ユーロ」を導入したが、イギリスはこれに参加しなかった。イギリスには大英帝国の盟主だったというプライドがあるので、自国中心ではない国際機関への参加には消極的で、大陸諸国も英米に対する警戒心が強かった。
ブリュッセルのEU委員会に行くと、イギリスとの文化の違いを感じる。基本的に政府を信用しないで市場に任せる英米人とは違い、大陸のヨーロッパ人は規制が好きで、キュウリやバナナの曲がり具合まで域内で統一しようとする。こうしたEU官僚の過剰介入には、イギリスはいつも反対してきた。
こうした葛藤が一挙に噴出したのが、イスラム難民問題だった。EUは域内の人の行き来は自由だが、EUに入るときの審査は厳しく、移民は制限していた。しかしドイツなどが低賃金の労働力を求めてトルコなどの移民を認めるようになったため、域外との人の交流も広がった。