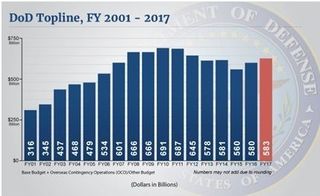シリア北西部ラタキア県のロシア軍基地で、出動の準備を整えるスホイ戦闘機(2015年12月16日撮影、資料写真)〔AFPBB News〕
外交面では互角以上に西側と渡り合い、その一方では国内経済が底なし沼にはまったかのように先が見えない――といった、ウクライナ問題発生以来のロシアの状況は相も変わらずのようだ。
多方面にわたるニュース種には連日事欠かなくても、鳥瞰すればロシアの歴史を動かす底流が、その時計の針を止めたかのようにすら思える。
それだけロシアが他に与える影響が、意外にも(特に日本では)目立たないからかもしれない。シェール革命やサブプライム問題を引き起こし、良くも悪くも世界全体を震撼させる米国とはやはりスケールが異なるのだろう。
ウラジーミル・プーチン大統領自らも「超大国を演じるようなコスパの悪いことなどやってられるか」と、ロシアがその器にあらざることを率直に認めている。
「ロシアは石油とガスの価格が回復し、欧米諸国が分裂し、ウクライナの体制が内部崩壊するのを待つしかない」とは、こうした今のロシアの一面を衝いている。
中東で存在感増すロシア
それでも、プーチン大統領のやっていることは、ウクライナでも中東でも、そして対西側でもすべてうまくいっていない、と米国の論者は、これも相変わらずのこき下ろしに余念がない。
裏返せば、ウクライナ問題とそれが招来した欧米との冷却し切った関係、そしてシリアの行方の始末をプーチン大統領がこれからどうつけて行こうとしているのか、への関心が隠せないということだ。
関心が向くのは、順風満帆からは程遠いにせよ、こき下ろされるほどにはロシアはまだヘタってもいないし、ヘマもしでかしてはいないからだ。むしろ問題の相手方の状況の方がより深刻になってきている。
そもそもの問題の発生源だったウクライナでは、腐敗一掃を目指した現政権が「ミイラ取りがミイラ」の体となり、その政権内では不和が絶えず、昨年2月に関係国と合意した約束事項(ミンスク-2)も果たせる見込みが立たずで、欧州、いや米国ですら、現政権を見る目が時を追うごとに冷たくなっている(最初から冷たかった本音が表に出始めた、と言うべきか)。
その欧州では、周知の通りの難民問題が、EU内での中欧や英国を巻き込んだ亀裂やドイツの政権不安定化にまで発展しかねないから、その爆発に至る導火線をどうにかして断ち切らなければならない。そのためには、ロシアを孤立化させるのではなく、国際問題(実際は難民問題の根源である中東問題)へ復帰させるべき、といった声も徐々に強まりつつある。
ドイツ銀行をはじめとする欧州商銀の業績不調と金融への不安も加わり、欧州にこれ以上ウクライナや中東などの他地域のことに構っている余裕などは、今後かなりの間にわたってありそうもない、と露紙は予測する。
そして昨今のシリア情勢では、複雑に絡み合う数々の関係者間に張られた網の目に、ロシアが自国の主張という糸を通しおおせているという結果が現れてくる。その和平調停に至るまでの流れは、どう見てもロシアの当初の台本とそのイニシアティブに従って進められているとしか言いようがない。