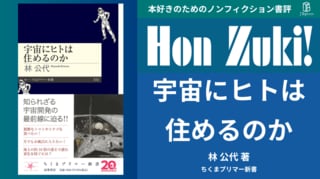日本人に食されてきた海苔には「贈りもの」としての歴史が連綿とある。海苔の進物品としての変遷を前篇では見てきた。
海苔は今もお歳暮に選ばれている。軽くて、しかも日持ちがよいという理由もあるのだろう。だが、そうした特徴が生かされるのも「誰もが美味しいと受け入れる風味である」という特徴があってこそだ。
海苔を食べる習慣が古くからあるのは、日本や韓国など東アジアの一部の地域のみ。世界的には稀有なこの食材を科学的に捉えて見ると、その風味と日本人の味覚の分かち難い関係性が見えてくる。
後篇では引き続き、東京・日本橋に本店を構える海苔の専門店「山本海苔店」に話をうかがう。海苔のプロが“海苔の美味”をどのように追求しているのか、その舞台裏を聞いてみたい。
11月から12月にかけては、海苔の「初摘み」の時期だ。
まず、海苔の“タネ”を牡蠣殻の中で培養しておく。そして秋、このタネが付いた「海苔網」を海に張っておくのだ。30日足らずで芽は伸びていき、摘み取りの時期になる。初摘み以降も、10日から15日で芽がまた出てくるので、二番摘み、三番摘みと重ねていく。さらに冷凍保存しておいた海苔網を海に入れ、春頃まで海苔を摘み取っていく。
有明海など日本の各地で採れた海苔は、生産者の手で海苔製造機にかけられ、紙状の海苔、つまり「浅草海苔」の形になる。この段階の海苔がいったん各漁業協同組合連合会にすべて納められ、入札にかけられる。そして、商社や海苔店に落札されると、あとは乾燥などの加工工程を経て、海苔製品として売り出されることになる。
筋金入りの専門職人が海苔を「仕訳」
「海苔の御三家」の1つとも呼ばれる東京・日本橋の「山本海苔店」は、海苔の品質管理を重視している。特に進物用の高級品からふりかけや佃煮などの自家用品まで、品質によって海苔を分類する技術を磨いてきた。
品質管理の伝統は、「味附海苔」を開発し、明治時代に同店を大いに発展させた2代目山本徳治郎にまでさかのぼる。2代目徳治郎は、それまで画一的に仕入れて売るだけだった海苔を、用途により8種類に分類したのだ。