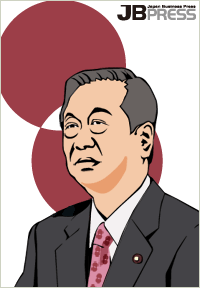民営化モデルから、公益性と地域性重視の郵政へ――。鳩山由紀夫首相のお膝元、内閣官房の郵政改革推進室が事務方を務め、郵政改革の議論が続いている。郵政改革関係政策会議はヤマ場に差し掛かり、2010年2月8日に資料まで入れると30ページに及ぶ「郵政改革素案」を公表し、改革の具体案を世に問い始めた。
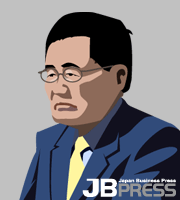 郵政改革担当、亀井静香金融相
郵政改革担当、亀井静香金融相
キーワードは「公益性の高い民間企業」が担う「政府の国民に対する責務」。しかしその素案の中には、経済学の専門家が首をかしげる大きな理論のねじれが2つ存在する。
ねじれの1つは、新しい日本郵政の経営形態の部分で見つけられる。
政策会議の素案は、日本郵政を「公益性の高い民間企業」と位置づけ、「電力やガス会社の公益性が参考になる」という。その上で、組織の性格を「民に担われながら公の役割を多分に受け持つ法人企業」としている。
 日本郵政の斎藤次郎社長
日本郵政の斎藤次郎社長
この経営モデルには先例がある。それは英国はじめ西欧が発祥の地と言われる「社会的企業(ソーシャルエンタープライズ)」のことだ。この「社会的企業」の事業モデルによれば、社会的課題の達成には、株式会社形態という市場メカニズムを活用したガバナンス(企業統治)の在り方がキモになる。
例えば、過疎地に住む高齢者などの社会的弱者が社会サービスから排除されるのを防ぐため、収益の上がらない活動領域で社会的企業は活動する。市場と政府の双方の失敗を補完し、政府では対応できない分野での活躍が期待されるわけだ。社会的企業は利益の見込める事業分野では営利企業として収益を上げる一方で、利益の見込めない事業分野では赤字覚悟で社会性のある事業を市場サービスの供給により営む。
過疎地のサービス低下不安に郵政を対応させるには、もってこいの事業モデルと思われるかもしれない。市場機能を活用するため、ある程度の収益も上げられるだろうし・・・。いいこと尽くめのようにも見える。
社会的企業の落とし穴、誰が統治するのか?
ところが、大きな落とし穴が待っている。それはガバナンス論の急所、すなわち誰が社会的企業を統治するのかが難しいのだ。
営利企業であれば、株主が経営者に経営を委託する。そして利潤がうまく上がるよう、株価や資本収益率などの経営指標を駆使しながら、経営者を監視していく。一方、政府の営む事業であれば、営利企業の株主に当たる納税者が政治家と官僚を投票や行政評価などで監視し、事業を遅滞なく進めさせていく。
これに対し、社会的企業のガバナンスは極めて困難だ。まず、「資本の論理」で非効率な事業を切ることはない。そうかと言えば、「納税者の論理」でガラス張りの透明性を確保しながら、国民の負託をいちいち問うような経営もしない。だから営利企業と政府の狭間で事業展開する社会的企業には、市場でも政府でもない、第3のガバナンス手段が本来必要なのだ。
ブレア政権下の英国では「監査の爆発」が・・・(参考写真)〔AFPBB News〕
悪くすると、経営者が市場尺度で測りづらい社会的価値の創出を隠れ蓑にして、放恣な経営に走ってしまう。あるいは、ぬるま湯のような社内ガバナンスを行うリスクもある。どうしても、民営化前の旧国鉄の惨憺たる経営状況を思い出してしまう。もっとも旧国鉄は100%お国の会社だったが。
だから電力やガスのように公益性の高い事業を営む企業に対しては、業務内容に厳しい許認可をかけて事前規制を行う。また、政府の事業を受託した場合には、英国のブレア政権下で発生した「監査の爆発」(「鳩山政権、周回遅れの『政治主導』」参照)とまで言われるような厳しい事後監査を数多く受け、業務の適切性をギリギリと問われることになる。
何れにせよ、社会的企業の制度設計の第一歩はガバナンスをいかに構築するか。そこから始まるはずである。