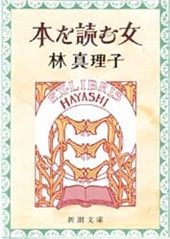私はコピーライターという職業を、林真理子の名前とともに知ったような記憶がある。まだ、子どもだった私には、それが具体的にどんな仕事なのかはっきりとイメージできていたわけではない。ただ、「流行を作る人」としてテレビ番組に引っ張りだこになっていたその女性が、露悪的な発言を繰り返すのが好きになれずにいた。(文中敬称略)
作家デビューのエッセイ『ルンルンを買っておうちに帰ろう』というタイトルも、いかにも軽薄な印象で、私は長い間、「林真理子読まず嫌い」だった。だから、初めて、知人から薦められて『本を読む女』を読んだ時、ずいぶんと意外な思いをした。
その文章は、「ルンルン」な気分とはほど遠く、軽薄さは微塵もなく、一文一文を味わいながら読みたくなるような、しっとりとした重みのある文章だった。
『本を読む女』は万亀(まき)という女性の少女時代から30歳過ぎまでを描いた物語。今の時代なら、女の子が一番面白おかしい毎日を送っている頃だ。しかし、舞台は昭和初期から太平洋戦争に敗れ、復興がようやく始まろうとする頃まで。日本中が貧しく、しかも、女の生き方に選択肢がなかった。
万亀も、希望通りの進学はできず、母親の敷いたレールに反発しながらも、あえてそこから踏み外す勇気もなく、いつも、心が完全に満たされることのない毎日を送る。見合いで一度会っただけの男と結婚し、その男を愛しているという実感のないまま戦争に送り出す。夫の出征中に生まれた長男は、すぐに病気で死んでしまい、夫の生死も知れぬまま年月は過ぎていく・・・。
満たされることなく、幸福とは言えない万亀を救ってくれるのは、いつも「本」だった。
女子専門学校に通っていた頃の万亀の言葉が印象的だ。「将来、何になりたいのか」――との友人の問いかけに対して、万亀はきっぱりと答える。「私、何にもなりたくないだよ。一生、小説とか詩の本を読んで暮らしていけたらいいなあと思う」
本好きの人ならば、誰でも、その気持ちが分かるのではないだろうか。何者にもならず、何の仕事もせず、ただ、陽のあたる温かい部屋で、来る日も来る日も、ぬくぬくと本を読んで暮らしていられたら・・・どんなに幸せだろうかと。
しかし、実際には、そんな都合のよい人生はどこにも用意されていない。生活をし、本を買うためには、お金がいる。そのためには職を得なければならない。煩わしい家族との関係、友人や同僚に理解されない苦しみ――ありとあらゆる現実とも折り合っていかなければならない。
結局のところ、万亀の人生は、万亀自身が生きなければならず、本の中の出来事はひと時の現実逃避にしか過ぎない。しかし、そのひと時が、また、万亀に現実と折り合いながら、次の一歩を踏み出す力を与えてくれる。
この物語の章立てには、「一章」「二章」という数字の代わりに、万亀が人生の節目節目で心を投影したり、救いを求めた本のタイトルが並ぶ。「赤い鳥」「放浪記」「斜陽」などなど。それは、恐らく、著者である林真理子自身も、大切に、読んだであろう本だ。
万亀のモデルは、林真理子の母親だそうだ。物語の中に、林真理子自身は登場しない。しかし、「本を読む女」から生まれた娘が、本を愛し、そして、本を書く女になったという昭和の女2代の歴史がしっかりと刻まれている。本を愛する人にとっては、切なく、味わい深い一冊だ。