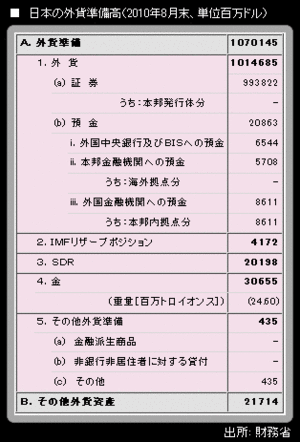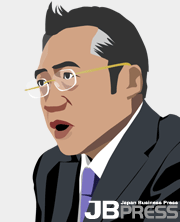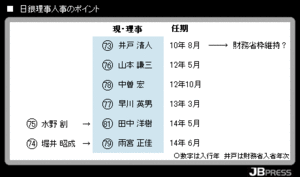サブプライムローン問題に端を発した金融危機で痛手を負った欧米諸国では、プルーデンス(健全性維持)政策の拡充議論が盛り上がっている。具体案の1つは、流動性供給を通じて常にプレイヤーの健康状態を把握し得る立場にいる中央銀行の権限強化だ。
しかし、世界に10年以上も先んじて金融危機を経験した日本に関して言えば、既に、行政も含めて過剰監督の弊害があるほど。これ以上の、日銀の権限強化は不要だ。また、日銀への監督権限付与は金融政策との利益相反が生じる恐れもある。
かつて、日銀には金融システムの監視と情報収集に特化した「営業局」という組織があった。日本独自の危機予防策として、営業局の復活を期待したい。
最も先進的マクロプルーデンス体制
ミクロプルーデンス機能を切り離した結果、危機対応に出遅れた(イングランド銀行)〔AFPBB News〕
プルーデンス機能がなかった!?(欧州中央銀行)〔AFPBB News〕
初代信用機構課長として、世界最高のプルーデンス体制構築に貢献(白川方明日銀総裁)〔AFPBB News〕
「プルーデンス」という言葉は一般的には聞き慣れないが、個別金融機関の健全性監視を通じて金融システム全体の安定化を図ることを意味する。日銀内では、個別金融機関の考査・監視を「ミクロプルーデンス」、金融システム全体の安定維持を「マクロプルーデンス」と使い分け、「金融機構局」がその任に当たっている。1990年代後半以降の危機を経て、試行錯誤を繰り返しながら、「世界的には最も機能するマクロプルーデンス体制を構築した」(幹部)と言っても過言ではない。
ここで注意すべきは、英米欧のプルーデンス拡充議論は、あくまで「不備のあった体制の立て直し」が目的である点だ。米国は監督体制がバラバラで、全体を統一的に見る機能が不十分だった。英国は、イングランド銀行がミクロプルーデンス部門を何年も前に切り離したことが裏目に出て、危機対応に出遅れた。欧州は、そもそも肝心の欧州中央銀行(ECB)にプルーデンス機能がない、という重大な欠陥を抱えている。
これに対し、日本は1998年6月に旧大蔵省から金融行政を切り離し、強力な権限を持った金融監督庁が誕生(その後、2000年7月に金融庁に改組)。片や、日銀は1990年代初頭の段階で、中央銀行界では先進的な「信用機構局」を設置し、マクロプルーデンス体制を整備した。ちなみに、白川方明総裁は、同局初代の信用機構課長だった。
行政当局と日銀が二人三脚で取り組んだ不良債権問題は、解決にこそ時間を要したが、金融危機が経済に大打撃を与えることを阻止。「リーマン・ショック」のような世界的失態を演じることなく破綻処理を遂行した。
つまり、日本より10年遅れのプルーデンス政策の拡充議論に、今さら日本が追従する必要はないのだ。
新日銀法施行で営業局は解体
日本ではむしろ「監督・監視が過剰で、経営は萎縮し、現場は疲弊している」(大手金融機関幹部)ことが大きな問題となっている。このため、プルーデンス体制の効率的運用に心掛けるのが現実的な対応だ。具体的に、日銀が取り組むべきは、冒頭で述べたように、金融システムの監視・情報収集に特化した組織を再構築することだ。
その前に日銀への行政権限付与について言及しておこう。中央銀行が金融機関の監督権限を握るのは、流動性を供給する立場も踏まえると一見合理的だ。しかし、「通貨」と「金融システム」の番人兼務は矛盾が生じ得る。例えば、大手金融機関が破綻の危機に直面して大量の資本を必要とし、中央銀行がこれに応じて巨額損失のリスクを負うと、通貨価値の劣化が懸念される。逆に、通貨価値の劣化を恐れて金融システムの番人役が疎かになるリスクもあり、番人兼務は慎重な検討が必要だ。