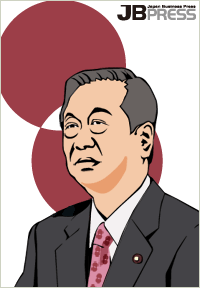米国史上最大の企業スキャンダル、それがエンロン事件だ。その内幕を描いた映画「ENRON:THE SMARTEST GUYS IN THE ROOM」(邦題「エンロン――巨大企業はいかにして崩壊したのか?」、2006年公開)を改めて観る機会を得た。その破綻の構図はリーマン・ショックと驚くほど似ており、その深層は今回の世界経済危機とつながっていると感じた。
エンロン創業者、ケネス・レイ元会長〔AFPBB News〕
そもそもエンロンという企業は、エネルギー事業に関する自由化をビジネスチャンスと捉え、配電業を独占するところからスタートした。さらに高度な数学に裏打ちされた、電力に関する新たな取引・商品を続々と開発。独占的な価格形成力を背景に巨額の利益を上げ、時にカリフォルニア州を大停電に追い込んだことは記憶に新しい。
エンロンは決算会計を巧みに操作しては、未実現の将来利益を時価評価でどんどん計上した。しかし、その時価評価は独占的な不完全市場での価格に基づいており、結局は足許の事業失敗に充てるキャッシュが手に入らず破綻した。こうした商品を開発し、取引を行っていたのは、「天才」と呼ばれる優秀な人材だった。
旧感覚のまま金融自由化、バブルに突入した邦銀
一方、リーマン・ショックでは、住宅ローンを材料にサブプライムのような新商品が生み出された。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)のような、実態とかけ離れた組み合わせ商品まで登場し、異常なレバレッジが掛けられ、決算書には巨額の利益が計上された。そこで取引された価格は、当人たちには合理的な説明がついていた。
だが、金融危機の勃発以降は実際にキャッシュを得ようとしても、実現益を伴うことはなかった。
BNPパリバ・ショックから2年・・・ (参考写真)〔AFPBB News〕
2007年夏のBNPパリバ・ショックのように混乱の兆候が表れると、当局者は「市場は新しい価格発見の過程にある」と繰り返す。今改めてこの言葉の重みを感じるのだが、問題となった市場の価格決定機能は相当に低下していたのだ。
同様に日本のバブルを振り返ってみると、それは金融自由化で新しいビジネスを求める動きの中で醸成が始まっていた。預金金利の自由化が進んでいるのに、運用収益とのバランス意識は銀行経営に未熟なまま。例えば、富士、住友両行が預金量トップ争いを演じた「FS戦争」は、規制金利下で量さえ確保すれば利益が保証されていた時代の名残だった。
旧感覚のまま邦銀各行は金融自由化時代を迎えてしまい、コストを掛けて集めた巨額資金の運用先はもはや保証されていない。その後の混乱が混乱を呼ぶ事態は、必然だったのだ。このように自由化という名の「怪物」は、どうやら行き過ぎた市場経済化やバブルを生む源泉のようにも見える。