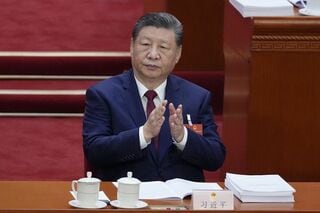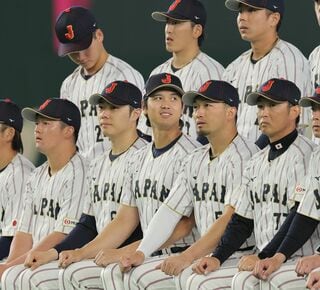昨年(2008年)8月のグルジア紛争から早くも約10カ月が経過した。この紛争がなんであったのか、ようやく冷静な議論がなされつつある。ロシアの膨張主義への警戒の声が上がる一方、西欧諸国は無謀な戦いに結果的に突き進んでしまったグルジア現政権に対する戸惑いを今も払拭できていない。
いずれにせよ、なぜロシアがアブハジアと南オセチアにこだわり、さらにその独立承認にまで踏み切ったのか。今春来日した著名なロシアの研究者マルケドノフ氏が、札幌と大阪で開かれた講演会でその点について発表したことがある。今回、彼が特別に興味深いリポートを送ってくれたので、これを参照し、批評も加えながら、もう一度その影響について考えてみたい(リポートはここからダウンロードできる)。
ロシアの内政不干渉政策も南オセチアは例外扱い
昨年の8月に起きた軍事衝突においては、紛争地帯を大きく踏み越えてグルジア領内にロシア軍が侵入し、軍施設を中心として破壊活動を行った。北大西洋条約機構(NATO)拡大に対する敵愾心、サーカシビリ大統領らグルジアの親西欧派エリートへの嫌悪感、コソボ独立問題で蚊帳の外に置かれたことなどが相まって、ロシアに極端なまでの行動を取らせたと一般には考えられている。
一方、マルケドノフ氏は、ソ連崩壊以降のロシアが基本的には新たに独立した近隣諸国への不干渉政策を採用していたが、その数少ない例外の1つが南コーカサスであったことを初めに指摘する。
広大なユーラシア国家ロシアにとって、隣接する諸地域の中で、南コーカサスが特に重要な意味を持つように通常は考えられない。また、カザフスタンやウクライナ、あるいはバルト3国のように、ロシア系の住民が多く居住するわけではない(多くの誤解が存在するが、南コーカサスにおけるロシア人の比率は極めて小さい)。
しかし、自身が北コーカサスのロストフ出身であるマルケドノフ氏は、ロシアはコーカサス国家であるとさえ述べる。それは、この地域が極端なまでに政治化された地域であって、ロシアは介入せざるを得ないと言うのである。その際に投入される資源とその費用対効果を巡っての政治および、そこに投影されるロシアのイメージは内政上、しばしば決定的な役割を果たしてきた。
要するに、グルジアを含め、この地域の特定の民族や小国家が好き勝手な行動を取ることをロシアは許さないし、許すわけにはいかない。これは、いわば大国の意地とも言えるものだが、ある意味「大国」意識の希薄な今の日本で理解が低い点に思える。
ロシアはコーカサスで万能な存在になり得ない
一方、実に厄介なことは、多民族地域コーカサスにおいては、ロシアは必ずしも万能な存在にはなり得ない点だ。また、過去の歴史を見ても必ずしもなり得なかった。つまり、一方の肩を持てば、もう一方はモスクワに恨みを持つことになるのである。
マルケドノフ氏は、今回のグルジアに対する軍事行動でも、北コーカサス内で領域紛争を抱えるオセット人とイングーシュ人のライバル関係が刺激され、イングーシュ人は大きな不満をモスクワに改めて抱いたことを指摘している。
また、内政だけではなく、グルジア紛争が典型的に示したようにコーカサスの様々な民族に対するロシアのスタンスが、国際関係におけるロシアのイメージにも大きな影響を与える。米国、欧州の資金が注ぎ込まれたグルジアで暴れ回った爽快感と裏腹の代償は少なくなかったし、今後ロシアはアブハジアや南オセチアの内政にもある意味責任を持たなければならなくなった。
いわば引くに引けないロシアは、現在まで強硬姿勢を貫き、先日は国連で拒否権を発動してグルジア紛争地域における国連監視団の延長すら拒絶した。いずれにせよ、今後どこまでメドベージェフがこの地域への関与を強めるか、その政治的嗜好性や、時の政権の自己イメージを考えるうえで、注目する必要がある。