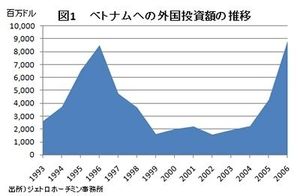1985年のプラザ合意以降に急速に円高が進み、また、90年代半ば以降に中国の製造拠点が大きく発展を遂げたことで、日本企業の生産拠点が中国をはじめとするアジア諸国に続々と移転していった。その結果、製造業の国内空洞化が声高に言われるようになった。
とりわけ過熱したのが中国への工場進出ブームだ。その中には、「出遅れてはならない」という切迫感に駆られた進出や、検討を重ねたとはいえ、進出することがあらかじめ決定事項になっているような雰囲気での進出もあったかに見える。
しかし近年の中国の人件費高騰や、昨年秋の金融危機以降の円高によって、工場進出を取り巻く環境は変化してきている。海外工場をどこに置くか、また、何を海外工場で作り、何を国内の工場(マザー工場を含む)で作るべきかを、改めて考え直す必要性に迫られているのだ。
日本同様に空洞化が進んだ台湾の製造業
工場の海外移転に伴う空洞化問題は、日本に限った話ではない。製造業への依存度が今よりも高かった80年代の米国では、製造業の空洞化が大きな問題であった。また、隣国の台湾や韓国でもいまだ日本より安いとはいえ人件費が高騰しつつあり、それに伴う工場の海外進出が問題となっている。
台湾企業の海外進出の中でも、圧倒的な比率を占めるのが、中国大陸への進出である。台湾から中国への直接投資累計額は、統計が公表された1991年から2004年までで412万ドルに上り、日本からの累計額315万ドルを大きく上回っている。
華南の広東省に進出している企業数を比較すると、2001年時点で日本企業の645社に対して台湾企業は5489社と8倍以上に達する。
これだけの規模で中国に進出しているということは、裏返すと台湾国内の工場の空洞化が日本以上のスピードで進んでいることに他ならない。
台湾企業による中国進出の3つのパターン
台湾企業の中国進出を観察すると、千篇一律というわけではない。スニーカー産業のように、台湾にほとんど何もなくなってしまった業界もあるが、そうした産業はむしろ少ない。大陸に進出しながらも台湾に拠点を残して、何らかの形で大陸の自社工場や中国の地元企業と分業している。それらの分業のパターンをまとめると、以下の3つに分けられる。
第1は、開発から量産までの機能分業パターンである。例えば台湾国内の拠点は、製品開発や設計、そして量産の立ち上げに特化し、量産展開は中国で行うというものである。
台湾に多いOEM/ODM(相手先ブランドによる生産/設計・生産)型の企業は、こうしたパターンが多いようだ。いまやノートPCの世界生産の7割以上を台湾企業が手がけているが、デルなど主要メーカーのノートPC生産を受託する最大手クアンタ・コンピュータの量産拠点も中国である。また、OEM企業として急成長を見せるホン・ハイ傘下の富士康(Foxconn)も、中国深センで4万人とも6万人とも言われる従業員を雇用して、各種電子機器の生産にあたっている。