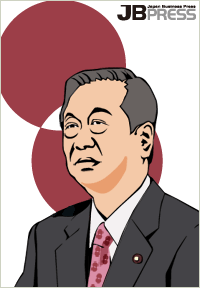2002年9月中旬、米国の首都ワシントンが1年中で最も快適な季節を迎える中、「第3回日米CSOフォーラム」が開かれていた。しかし、日米双方の参加者の苛立ちが、爽やかな初秋の空気を切り刻んでしまった。
CSOとは、市民社会活動団体(Civil Society Organization)の略。非営利の市民団体はNGOやNPOとも言うが、国際的な会議ではCSOと呼ばれることが多い。このフォーラムには、日米両国の国際的なCSOから、そうそうたる代表が参加していた。
お互いの「苛立ち」の中身を説明しよう。当時、ブッシュ前政権によるイラク開戦(実際は2003年3月)を控え、日米CSOのお互いに対する期待は噛み合わなくなっていた。
日本のCSO関係者の多くには、「どの国のCSOでもCSOである以上、反戦・反政府であるはず」との思い込みがある。例えば、日本のあるCSO代表は東京の本部から、「イラク開戦反対」を唱える米国CSOの声を集めて来いと指示され、その取材に廊下を駆けずり回った。
そして、その姿が米国CSO側の反発を秘かに招いていた。米側の大半は、「戦争は不幸なことだが、それによって大量に発生する難民の支援や、戦災地の復興支援が国際協力CSOの腕の見せ所であり、世論へのアピールの源泉だ」と考える。それに向けて日米CSOは事業展開や資金集めを検討すべきなのに、構想さえ持てない日本のCSOの未成熟ぶりに米側は業を煮やした。
米側の不審の眼差しに対し、日本側は「日本のCSOを米側は資金集めの手足、あるいはカネヅルとしか見ていないのか」と一層反発を強めていく。
日米同盟を発展、宮沢喜一元首相〔AFPBB News〕
日米CSOフォーラムは、日米同盟を地球規模問題の対処にも適用する「日米コモン・アジェンダ」に基づく、ハイレベルの外交的枠組みだ。1993年、当時の宮沢喜一首相とクリントン米大統領が合意した。
官だけでなく、民も地球規模での問題解決に向け、日米が連携すべきだ――。この高邁な理念の下、日米パブリック・プライベート・パートナーシップが打ち出され、2000年1月には第1回日米CSOフォーラムがホノルルで開かれた。
それから、わずか2年余。冒頭で紹介したように、日米のCSOが見解の相違を露呈した。「日本のCSOとはもう話したくない」。第3回会議の終了間際、米国の有力CSOの代表は傍聴者の1人にそう吐き捨てた。
アリとゾウ、日米CSOの資金規模
日米CSOの我彼の差は、イラク戦争をめぐる考え方だけではない。職員の収入とキャリアアップの仕組み、事業規模、資金の集め方・・・。どれを取っても、米国のCSOは成熟しており、豊かだ。他方、日本のCSOには、自己犠牲に満ちた切迫感と資金不足が目につく。
大阪大学NPO研究情報センターが2004年公表した「NPO白書2004」によると、日本の寄付金の経済規模は8385億円。これに対し、米国はその20倍あり、2035億ドル(約18.3兆円)に達する。「寄付金経済」はケタ違いなのだ。
「ペイ・スケール」という米国の給与比較サイトを見ると、米国ではNPOの事務局長の平均年収は勤続5~9年で5万4000ドル。10年を超えると6万3000ドル、20年以上では7万5000ドルと昇給していく。日本に比べて物価の比較的安い米国では、これだけの給与があれば贅沢を望まない限り、家族を養い生活できる。他の職種との比較でも自営業より高く、公務員や教師より若干落ちるぐらいの水準だ。
また、国際CSO「大手」の米国法人である Oxfam America や CARE USA の高級スタッフ履歴を見ると、大手投資銀行で活躍、資産1兆ドル超を運用する投資信託会社CEOから転職、元市議会議長、米国際開発庁(USAID)や国連機関で勤務・・・。こうした職歴がずらりと並んでいる。CSOの高級スタッフは、彼らにとってワシントンの「回転ドア」の一コマに過ぎない。大使経験者をトップに戴くCSOさえあるのだ