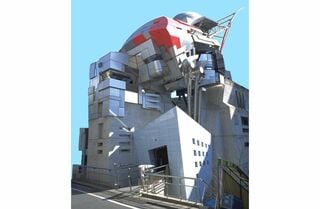しかし、我が国との間に存在する北方領土問題をめぐってはそうした行動には出てきません。それどころか、まるで日本を見透かしたかのように返還するのかしないのか分からない態度を取り続けている。
択捉島の北側には極東最大のロシアの原子力潜水艦基地がありますが、思うにこの場所に軍事基地が存在する限り、ロシアは領土を手放さないはずです。
ロシアが返還しない理由は他にもあります。日本列島を逆さまに回転すると、ちょうど北方領土の場所に沖縄がきて、逆に北方領土の位置に沖縄がきます。すなわち、米国から見た沖縄というのはロシアから見た北方領土と同じ意味を持ち、こうした地政学的な事情も背景にあると考えられるのです。
太平洋上に原子力潜水艦を自由に展開させるためにも北方領土はロシアの軍事戦略上欠くことのできない要衝ですから、平和ボケの感覚では交渉を勝ち取るのは難しいでしょう。
大切なのはまず米国との日米安全保障条約をしっかりと保持すること。日米の協調関係があるという前提をベースに話をしなければ、ロシアは首を縦に振らないはずです。
言うなれば我が国は、米国の安全保障という「核の傘」があったからこそ、軍事力を持たずとも世界中でビジネスを展開し、経済成長を成し遂げられたわけで、今こそそうした日米関係の背景を再認識すべきではないでしょうか。
プーチン大統領が展開するウクライナ外交を見ていると、冷戦時代に戻ったような感覚を覚えます。21世紀の今、20世紀の米ソ冷戦構造に照らし合わせながら国際情勢を考えることも大切だと思います。
政府の秘密指定を公平・公正にチェックできる仕組みづくりを
続いては国内の話題です。今年12月までに施行される特定秘密保護法について、秘密保護法制に詳しい米国の元政府高官が9日夜、東京都内で講演し、法律の運用にあたっては恣意的な秘密指定を監視するチェック機関が重要だと指摘したと報じられました。
講演したのは米国の国家安全保障会議の上級部長などを歴任し、秘密保護法制をめぐる国際的なガイドラインの作成にも携わったモートン・ハルペリン氏で、ハルペリン氏は同保護法について「日本政府は市民や国際社会の専門家と十分に協議をせずに法律を制定した」などと批判。
そのうえで「法律の運用にあたっては、たとえ省庁が反対しても秘密の開示を命じることができるような機関を持つことが望ましい」と述べたそうです。
このハルペリン氏の指摘は、ある部分では正しいと思います。しかし、日本政府の協議が十分でなかったかどうかは意見の分かれるところであり、私は必ずしもそうは思いません。
ただ、記事でも伝えられているように、政府が恣意的な秘密指定を行う可能性は否定できませんし、それを監視するチェック機関が重要だという指摘はもっともです。どんな政党が政権を握ろうとも、政府に対する不安感や不信感を払拭する意味において、公平・公正にチェックできる仕組みづくりは非常に大切だと思います。
なお政府与党では今、自民党の「インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチーム」座長の町村(信孝)元官房長官を中心に議論を深めながら、同盟国各機関の関係者を招き、さまざまな意見交換を行っているところです。