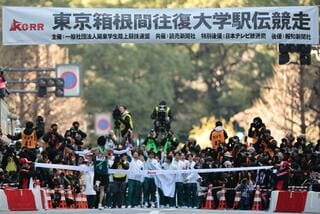知らない人も多いと思うが、日本の江戸時代、彫り物のストラップが大流行していた。それが根付だ。紐を通した根付は、印籠や煙草入れや小袋に付ける実用品だった。
当時、根付は武士も町人も、主に男性が使っていたという。着物はポケットがないので、小物に付けた根付ストラップを帯に挟んで歩いていた。女性は着物の懐に小物を入れることが多く、根付はあまり必要なかった。
 蓮齋(れんさい)が作ったキノコと蛙。キノコの傘、柄、蛙の丸みが、なんとも滑らか。非常に密な傘のひだも美しい。傘の表面にある2つの穴に紐を通す。根付は、大名同士が会うときの手土産としても使われたそう(写真提供:特記以外すべてAlain Ducros) 拡大画像表示
蓮齋(れんさい)が作ったキノコと蛙。キノコの傘、柄、蛙の丸みが、なんとも滑らか。非常に密な傘のひだも美しい。傘の表面にある2つの穴に紐を通す。根付は、大名同士が会うときの手土産としても使われたそう(写真提供:特記以外すべてAlain Ducros) 拡大画像表示
片手にすっぽりと収まるこの小さな彫り物のモチーフは、実に多種多様だ。人、顔、動物、植物、虫、仙人や神、鬼や妖怪、ダルマ、橋や蝋燭など、どれも目を疑ってしまうほどの実に見事な仕事をほどこしてある。
いまは美術館で見るのが普通のこの古美術は、根付師たちが作っていた。その数は、登録されていただけでも3000人もいたという。
しかし、明治時代に入って洋服の時代になり、生活必需品だった根付はお役御免となった(ただし鑑賞用としては作られていた)。そして、日本を訪れた外国人たちが根付の秀逸さに魅了されて、根付は次々に海外に持ち出されていった。
そんな根付を、ふらりと訪れたロンドンの美術館で、55年前に初めて見た若いフランス人がいた。いまや、根付に関わる人の間では誰もが知っている根付専門家アラン・デュクロ氏だ。
デュクロ氏は胸を高鳴らせながらすぐさま館長に話を聞きに行って、根付の話に魅了された。パリで英語教師をする予定だったデュクロ氏の運命の方向は、その日から少しずつ根付の世界へと動いていった。
パリに住むデュクロ氏はいまも日本を定期的に訪れて、まだ隠されている根付の謎をひもといている。
食事よりも根付が大事! 根付に惹かれていった日々
京都に根付専門の美術館「京都清宗根付館」があったり、東京国立博物館には現代根付の定期展示「根付 高円宮コレクション」があるが、根付は日本ではあまり強い関心を持たれていない美術だろう。
一方、海外では高く評価されている。根付を所有する美術館は多いし、熱狂的な収集家たちも多い。精巧な技術やモチーフの多様性、生活世界をこんな小さなサイズで表現している点はやはり驚異的に映っている。
デュクロ氏は、36年前に『Netsuke et Sagemono』(絶版)という根付と提物(さげもの、印籠・巾着など腰に提げて持ち歩くものの総称)の解説書をフランス語で出版した。この本で、江戸時代にどんな根付師がどんな根付を作っていたかを細かに説明した。