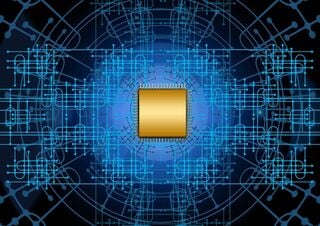北九州市(福岡県)がなぜ世界有数の環境都市になれたのか──。それを知るためには、時計の針を半世紀近く巻き戻さなければならない。
今をさかのぼること四十数年前の映像だ。
1960年代半ばの北九州。長屋の一角のような小さな家の中の様子が映る。部屋には扇風機が置いてある。買ってからまだ2カ月しか経っていないというのに、その羽根は黒くべっとりと汚れている。
近所の工場の煙突から出た煤煙が部屋の中まで入ってきて、扇風機の羽根にこびりついているのだ。
「この羽根が家の中の空気をかき回すかと思うと、もう北九州にはいたくないと思います。でも、この住宅事情ではおいそれと家はなく、出ていくことはできません」──。女性の悲痛なナレーションの声が耳に響く。
これは、ある記録映画のワンシーンだ。タイトルは「青空がほしい」。北九州の工場周辺に住む主婦たちが自主制作でつくった8ミリ映画である。制作されたのは1965年。公害がエスカレートし、住民たちの健康を、いや、生命を脅かしていた頃だ。
明治時代に富国強兵政策のもと、北九州に官営八幡製鉄所が設立され、日本の近代化の拠点となったのはご存じの通り。その後、北九州には製鉄、化学、機械など重厚長大産業の工場が密集し、「4大工業地帯」の1つと数えられた。
だが、戦後になって高度経済成長の波に乗り繁栄を謳歌する一方で、公害という深刻な病いに侵されることになった。
林立する煙突からは煤塵、煤煙、亜硫酸ガスなどが吐き出され、周辺住民の上に降り注いだ。ぜんそくや扁桃腺炎にかかる住民があとを絶たなかった。
海や川は壊滅状態だった。工場から強酸性の汚水が流れ込んだ洞海(どうかい)湾は、魚はおろか大腸菌さえも棲めず、「死の海」と呼ばれた。船のスクリューまでもが腐食して溶けたという。まちの中心を流れる紫川にも、油や薬品を含む工場排水が流れ込んだ。川底にはヘドロがたまり、異臭が漂っていた。
5000人の海外研修者が北九州で学んでいった
そんな絶望的とも言える公害のまちで、住民たちはまさに生きるか死ぬかという思いで、生活環境の改善を希求した。その追いつめられたエネルギーがうねりとなって企業と行政を突き動かし、まちの姿を変えていくことになる。