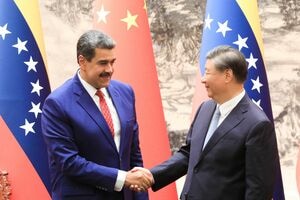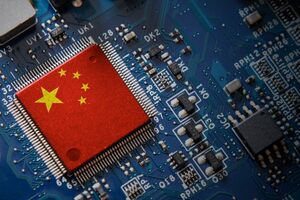しかし、これらの動きをもってミャンマーが民主化に向けて大きく舵を切ったと断言することはできない。
最近のミャンマー政府の姿勢はあくまでポーズに過ぎず、米国のためにミャンマーが対中関係を犠牲にすることはない、というのが現時点での大方の見方であろう。
現在ミャンマーが必要としているのは、国内経済の立て直しと、それを可能にする外国からの直接投資だ。しかし、こればかりは中国から得ることができない。そのためには、西側、特に米国との関係改善も同時に必要になる、とミャンマー新政権は腹を括ったのだと思う。
実際に、ミャンマー側の動きは極めて慎重かつ漸進的であり、急激な方向転換は考えていないようだ。
恐らく、セイン大統領は今後も様々な国内の民主化、自由化措置を導入して米国等との関係を徐々に改善しつつ、中国との伝統的友好関係をも可能な限り維持しようとするのではなかろうか。
それにしても、ここまで中国をコケにして、対中関係は大丈夫なのか。ミャンマーのやり方は、良く言えば「等距離外交」、悪く言えば「二股外交」だ。米国との関係改善も結構だが、米中を手玉に取るような外交が本当に長続きするのだろうか。他人事ながらちょっと心配になる。
中国にとり戦略的に重要なミャンマー
ミャンマーは中国にとって戦略的に重要と言われて久しいが、正直なところ、筆者もつい最近までミャンマーの地政学的重要性を過小評価してきた。
この点は大いに反省している。ミャンマーの重要性を理解する最も手っ取り早い方法はミャンマーの地理をじっくりと見ることだ。右の地図をご覧いただきたい。
まず驚くのは、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国でありながらミャンマーがベンガル湾、アンダマン海に面していることだ。
当然ながら、ミャンマー最大の都市ヤンゴンも、南シナ海側ではなく、インド洋側に位置する。ミャンマーは筆者の想像以上にインド文化圏に近いことがよく分かった。