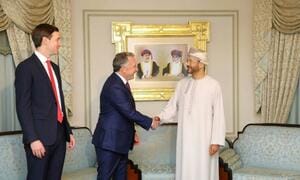2. イスラエルの核保有に至る歴史的背景: スエズ動乱の衝撃
イスラエルの核保有は「公表された秘密」である。米国の秘密解除された大量の文書から、1975年までには、米国はイスラエルが核兵器を保有していることを確信するに至っている。
イスラエルは、その最も初期の段階から核の選択肢についての調査を行っていた。1949年には2年間のネゲブ(Negev)砂漠の地理学的調査を開始している。
1852年にはイスラエル原子力エネルギー委員会が設立され、「二度と虐殺の羊にはならない」ための最善の道として、核爆弾に長年にわたり専念してきたアーネスト・デビッド・バーグマン(Ernest David Bergmann)が議長を務めた。
彼は同時に国防省の研究インフラ部長でもあった。その指導下のMachon4と呼ばれる研究機関では、1953年までに、ネゲブ砂漠で発見されたウランの抽出法と重水の生産技術を開発した。
原子炉の開発ではイスラエルはフランスの援助を求めた。両国の協力関係は1950年代の初めにまでさかのぼる。フランスは、40メガワットの重水を使った原子炉の建設をその頃に始めた。
両国政府は、冷戦時代の二極体制の下で、ある程度の自治権(autonomy)を確保するための手段と、独立した核の選択肢をみなしていた。1956年の秋には、フランスはイスラエルに18メガワットの研究用原子炉を供与した。
その数週間後に起こったスエズ危機は事態を大きく変化させた。英仏とイスラエルは、イスラエルがエジプトとの戦争を起こし、英仏が平和維持のために軍を派遣することで合意した 。
スエズ危機の時、ハンガリーでは暴動が起こり、ソ連はその対応に追われていた。フランスはアルジェリアの反乱に悩まされ、米国ではドワイト・アイゼンハワー大統領が2期目の選挙戦の結果待ちの状況にあった。
このような米ソが動きのとれない中で、1956年10月29日夕刻、イスラエル軍によるスエズへの奇襲侵攻が開始された。
空挺部隊がシナイ半島のミトラ峠に降下し、3方向から地上師団がシナイ半島の国境から侵攻、1週間でシナイ半島の全域とスエズ運河の東岸を占領した。
イスラエルはこの際にエジプトの戦争能力を奪うことができ、参戦の代償としてフランスから原子炉の供与を受けることも保証される。さらには、シナイ半島を平定することを目論んでいた。
11月5日と6日、英仏両軍はスエズ運河の都市を空挺部隊と海兵隊で占領した。このような動きに対し、米国は、アラブ諸国の指導者が反発してソ連側につき、中東へのソ連の自由な介入への道を開くことを恐れた。
特に英国の参戦は意外であり、アイゼンハワーを怒らせた。ロンドンでは労働党が参戦に反対し、ポンドは下落し、米国はポンド安定化へ協力を拒否した。
フランスでは、アルジェリアの反乱を抑えるためととられ、戦争は正当化された。迅速な勝利は3国に安堵をもたらし、イスラエルは勝利を宣言した。
しかしその直後に、最も危惧されていたソ連の介入が始まった。ソ連から11月6日の勝利宣言の数時間後、英仏両国には同文の、イスラエルにはそれよりもやや表現の柔らかい最後通牒が届けられた。
フランスに届いた通告では、「ロシアが核兵器を保有していることを忘れてはならない。もしも空挺大隊の降下を中止しなければ、それらを貴国に対し使用するであろう」と明言されていた。
同日、米ソ両国は英仏に対し、撤退を宣言するよう強要した。国連軍が両国に取って代わることになった。
イスラエルに対する最後通告では、「イスラエル政府は、平和とその市民に対して無責任で犯罪的な行為を行っており、イスラエルの国家としての存続に疑がいを持たせている」とされていた。
さらに「ソ連はミサイルでイスラエルを攻撃できる」との警告もされた。国連ではイスラエルの撤退が賛成68、棄権10、反対1で可決された。英仏は棄権し、イスラエルのみが反対した。
フランスはイスラエルに「ロシアが、中東への介入の準備をしており、その第1目標はイスラエルへの攻撃である」と告げた。
その前日アイゼンハワーは第2期目の大統領に選ばれ、圧力を加えることができるようになった。
イスラエルに示された警告は、「シナイからの撤退の拒否は、世界の平和を危機にさらすものである。ソ連がもしも軍事的に介入すれば、第三次世界大戦になるおそれがある」とし、イスラエルの米国によるすべての援助は停止され、国連のイスラエルに対する制裁を支持するであろうとするものであった 。
ソ連の3国に対する恫喝は、とりわけイスラエルに、潜在的に信頼できない同盟国に依存するのを止めるために、独立した核能力が必要であることを認識させたのみではなく、フランスの指導者に、友好国に対する支援の約束を十分に果たせなかったとの、負い目を感じさせることになった。
フランスは、イスラエルに対して核爆弾という「貸し」を負うことになったのである。