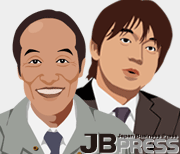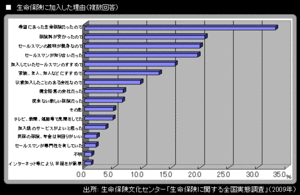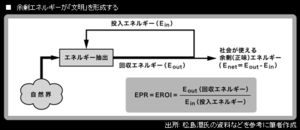しかし、戦後50年続いた「冷戦」が1989年に終焉を迎えた。ベルリンの壁の崩壊に象徴されるように、世界の政治・経済を東西両陣営に厳しく峻別していた高い壁は一挙に崩れ去った。その時点で「反共」の自民党は政権党としての必然性を失った。
しかも同時に、経済成長も続かなくなった。2回の石油ショックで高度成長が終わり、バブル崩壊で「失われた時代」に迷い込んだ。少子高齢化、経済のグローバリゼーション、さらには財政赤字、環境問題などが現れているというのに、有効な解決策を見出せない。
「反共」という政治的な「必要条件」だけではない。自民党を支えていた経済成長という「十分条件」も失ってしまった。54年続いた自民党支配は、終わりを告げるしかなかった。
民主党は自民党と何が違うのか?
それなら、総選挙で大勝した民主党に政権党としての必然性はあるのだろうか。
つまり、民主党政治が根底的に一体何を目指すのか。その方向性は時代の要求に合致しているのか。さらには政策を具体的に展開する財政的基盤はあるのか、である。
「必要条件」も「十分条件」も満たせずに、政権与党から滑り落ちた〔AFPBB News〕
民主党政治は自民党のそれとどう違うのか――この春、民主党のある有力議員にこう聞いた。その答えは、「8割程度はあまり変わらない。どう違うかより大事なのは、政権が交代することだ」だった。
あたかも権力至上主義である。実際、総選挙の民主党の最大のスローガンは「政権交代」だった。マニフェストに並ぶいくつもの政策より、大きな声で叫ばれたのは政権党が交代することの必要性だった。
交代して何をするのか。それがはっきり見えてきたのは新政権のスタート後である。八ッ場ダムの建設中止、子ども手当の創設、補正予算の執行停止、無駄な予算を洗い出す「事業の仕分け」。
矢継ぎ早に打ち出される政策は明らかに自民党時代のものとは違っている。「コンクリートから人へ」である。それこそが民主党政治が目指すべき理念、つまりは政権を特徴付ける「必要条件」だったのだろう。確かに時代の要求にも合っていた。
それなら、その理念を実現するための「十分条件」は、先行きが見えなくなってしまった日本経済の活性化であるはずだ。