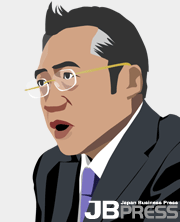日本郵政を相手に吠え続けてきた鳩山邦夫総務相が6月12日、ついに辞任した。
指名委員会の決定にも不満!(資料写真)〔AFPBB News〕
資本金3兆5000億円、日本最大級の企業が機関決定した経営方針を「癒着」の一声で白紙撤回させ、社外取締役が過半を占める指名委員会で決定した西川善文社長の続投を「お手盛り」と断じ、最後は「正義」を振りかざした一連の発言にどれだけの根拠があったのか定かではない。言い掛かりのような主張で、「ルール」を超越した政治介入を平然と繰り返した責任は重い。
海外投資家から見れば、この騒動は「カントリーリスク」以外の何ものでもない。
つい1年ほど前まで、政府が声高に掲げていた「対日投資倍増」の目標が、麻生政権下では全く聞かれなくなったのは、世界的な金融危機だけが理由ではないだろう。
サブプライム問題をきっかけに世界の金融・資本市場は大きく下落したが、「欧米に比べ、影響は限定的」と政府が説明してきた国内市場は、海外のどの市場よりも落ち込み幅が大きかった。本来ならば、傷の浅い日本市場に海外資金が流入してもよかったはずだが、そうはならなかったのは、世界共通言語である「コーポレートガバナンス」の重要性を理解していなかったツケだ。
日本郵政は政府が100%出資する特殊会社。しかも、小泉純一郎元首相が党内や郵政職員の抵抗をねじ伏せて民営化に漕ぎ着けただけに、改革の後戻りを警戒した当時の竹中平蔵郵政民営化担当相が「特殊会社の将来にわたる適切な業務運営の確保のためには、主務大臣の関与が必要だ」として、コーポレートガバナンス(企業統治)に政府が関与する仕組みを作った。
経営の意志決定は、一般の企業のように取締役会と株主総会だけでは完結せず、取締役選任や事業計画、定款変更など、経営の根幹に関わる部分が、総務相の認可事項とされている。このいびつさが鳩山邦夫氏の暴走を許し、海外投資家に日本のコーポレートガバナンスに疑義を抱かせたのはなんとも皮肉である。
カバナンス無き国のガバナンス議論
郵政騒動が永田町を巻き込み盛り上がりを見せ始めていた頃、霞が関では「コーポレートガバナンス」をめぐる2つの議論がひっそりと幕を閉じた。
金融庁の金融審議会「金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ」と経済産業省の「企業統治研究会」だ。共に、日本企業のコーポレートガバナンスの脆弱さが国内マーケット地盤沈下の要因になっているとの問題意識から、2008年秋から有識者による議論を重ねてきた。
徒歩わずか2~3分の距離にある2つの役所が、同じ時期に、同じテーマをそれぞれに議論している程度の統治能力しか持ち合わせない国が、ガバナンスを論じること自体が漫画のような話。その上、半年以上の議論を経て得られた結論が、「日本には日本の良さがある」という身も蓋もないような内容だった。