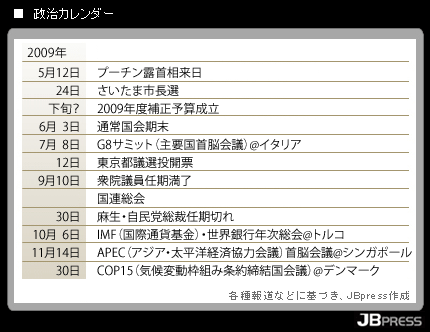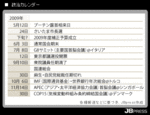改革旗手も世襲引退〔AFPBB News〕
残り0文字
世襲議員といえば、安倍晋三、福田康夫と2代続けて政権を放り投げた両首相が思い出される。この2人は近年の世襲批判を招き、「ひ弱」で「頼りない」というイメージも増幅してしまったのかもしれない。
また、引退表明した小泉純一郎が次男の進次郎を後継指名したことにも、批判は少なくない。小泉は「親ばか」と釈明したが、結局は選挙区の既得権益を手放したくなかったのだろうか。
世襲の弊害は、世襲でない有能な人材の政治参加を阻むことだと言えよう。自民党の平沢勝栄はフジテレビの番組で「世襲でない優秀な人が政治に参加したくても、どうしても世襲候補は有利な立場にある。一般の国民で政治を志す人がなかなか入って来られない」と指摘した。
「たたき上げ」の危機感
 たたき上げの菅氏「世襲制限」
たたき上げの菅氏「世襲制限」
菅は秋田県の農家出身。会社員や横浜市議を経て、1996年衆院選で初当選した「たたき上げ」の政治家だ。5月3日、テレビ朝日の番組で世襲制限を提唱した理由を聞かれると、菅は「自民党が特定の人たちの政党で国民の目線からずれている、と国民から思われているのではないか」との危機感を示した。
中選挙区制時代は、政治家が引退するとその選挙区で激しい後継争いが演じられた。政治家の息子や秘書、県会議員らが出馬を争い、候補者一本化調整に失敗すれば、それぞれ無所属で出馬した。
だが、小選挙区制に移行してからは政党中心の選挙となり、このような無所属候補はよほど知名度がない限り、当選が困難な状況となった。こうした現状を放置すれば、菅は党がますます活力を失ってしまうと危惧する。だからこそ、「自民党の体質が問われている」と体質改善の必要性を訴え、その具体策として世襲制限を打ち出したのだ。
世襲制限、民主が先行
民主党が自民党に先んじて国会議員の世襲制限に踏み切る方針を決定したこともあり、菅は選挙対策上も後に引けなくなった。
民主党は4月23日、国会議員の子どもや配偶者など一定の親族が同一選挙区から連続して立候補することを制限する方針を決めた。親族の範囲については、3親等以内とする方向だ。
世襲問題では、政治資金管理団体を親から子へ引き継ぐ場合などに非課税となる制度も批判を浴びており、民主党は政治資金規正法の改正も検討している。資金管理団体の継承にどう対処するか、自民党は姿勢を厳しく問われることになる。
反「世襲制限」、鳩山総務相(参考写真)〔AFPBB News〕
一方、菅が4月に入って世襲制限をぶち上げると、自民党内からは「職業選択の自由に反する」(総務相・鳩山邦夫)などと、反発の声が続出した。世襲議員にしてみれば、自らの存在意義を否定されるだけに、衆院議院運営委員長の小坂憲次は「私は世襲の権化みたいなもの。世襲禁止を決めるならそれなりの覚悟を決める」と怒りをあらわにした。
自民党の選挙公約プロジェクトチーム(PT)の座長に内定している菅にマニフェストづくりを主導させまいと、PTの上部機関として幹事長の細田博之幹事長をトップとする選挙公約作成委員会が設けられた。一部の党幹部が菅の抑えこみを狙い、作成委でPTをチェックできるようにしたのだ。これに対し、菅は世襲制限に賛同する同志を集め、議連結成で対抗する構えだ。
もっとも、こうした党内対立がどこまで激化するか、依然として不透明な状況だ。菅が検討しているのは、親族と同一選挙区から出馬する世襲候補は公認しないという内容。だが、こうした世襲制限をマニフェストに盛り込んだとしても、実施は「次の次」の衆院選から。果たして、次の衆院選後に公約が実現するかどうかも疑わしい。
ここは、自民党の論議と本気度をしっかり見る必要がある。衆院選を控え、改革に消極的と思われたくない世襲議員が反発を抑え、沈黙する可能性さえ否定できないのだ。既に自民党内には、世襲制限に慎重姿勢を示していた議員がマニフェスト盛り込みを容認するムードさえ出始めているという。今さら世襲制限に反対して、自民党を離党するような議員はまずいないだろう。「郵政選挙再現」と言っても、時の宰相の器が違い過ぎることを忘れてはならない。