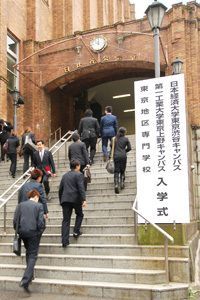文楽の舞台の上は、当然のことながら人形が主役だ。人形に命を吹き込む「遣い手」は本来、裏方にすぎない。自らの存在を消すため、その基本スタイルは足元まで覆う黒衣、黒い手袋、黒い頭巾・・・と全身黒ずくめ。しかし、ファン心理とは身勝手なもので、「あんな切ない乙女心を表現できるのは誰?」「切れ味鋭い、侍の動きをする人形遣いの顔が見てみたい」と、遣い手に関する興味が抑えられなくなってくる。
 連日「満員御礼」、国立劇場(東京・隼町)
連日「満員御礼」、国立劇場(東京・隼町)
そんなファンの声に応えるのが、「出遣い(でづかい)」という演出。主遣い(おもづかい)、左遣い、足遣いの3人1チームのうち、メーンプレーヤーの主遣い(首と右手の動き担当)だけは頭巾を被らず、顔を出して舞台に上がるのだ。顔が見えれば、ついつい惚れてしまうのも、これまたファン心理。かくして、主遣いクラスの人形遣いの中には、舞台から降りてもスター的な存在の人も多い。
かつては、主役の人形を遣う超ベテランだけが、例外的に顔出しで舞台に登場していた。プログラムに「この演目のこの人形は出遣いでやります」とわざわざ書かれるほど、特別なファンサービスだったという。
ところが、最近の文楽の公演を見ていると、どんな端役の人形であっても、主遣いは顔出しで登場するのが通例だ。その結果、舞台の上は「顔」だらけになってしまう。例えば、登場人物が10人の場面ならば、人形と遣い手で合計20もの顔が、狭い舞台の上にひしめく。見慣れていない人にとっては、顔、顔、顔のオンパレード・・・。一体、何に注目すればいいのか、混乱の原因になることもある。
黒ずくめの20年、主役には40年も
「出遣い」が増えた背景には、後継者問題が存在する。毎年、日本芸術文化振興会は研修生を募集し、2年間にわたって技芸員となるための基礎的な技能や教養の指導を行い、後継者育成の端緒としている。とはいえ、テレビでほとんど紹介されることもなく、普通の中高生にとっては、存在しないも同然の世界。星の数ほどデビューしては消えていく歌手やお笑い芸人のように、大量の新人が集まってくるわけではない。
しかも、2年間の研修期間を終えたところで、ようやく技芸員の元に入門が許され、本格的な修業の日々が始まる。初舞台にこぎつけても、人形遣いの場合は足遣い、左遣いの約20年間は頭巾を被った黒ずくめ。プログラムに名前が載ることもなく、ひたすら無名の存在として舞台に立ち続けなければならない。
昭和ならともかく、豊かな時代に生まれたイマドキの若者が、気の遠くなるほど長く、地味な下積み生活を乗り越え、主遣いの座にたどりつく・・・。それは奇跡に近いように思える。主役の人形を遣うようになるには、そこからさらに15~20年の歳月を要するのだ。