 Pond Saksit/Shutterstock.com
Pond Saksit/Shutterstock.com
将棋に「定石」があるように、ビジネスには経営学者や実務家によって開発された「フレームワーク」がある。思考を助ける枠組みであり、アイデア創出やニーズの発見、課題の洗い出し、戦略立案、業務改善など、活用シーンはさまざま。その概要と使用法を心得ておくことが、ビジネスパーソンにとっての大きな武器となる。
本連載では、事例・参考例が豊富な『ビジネスフレームワークの教科書 アイデア創出・市場分析・企画提案・改善の手法55』(安岡寛道、富樫佳織、伊藤智久、小片隆久共著/SBクリエイティブ)から、内容の一部を抜粋・再編集。
第2回は、顧客の意見を商品開発に反映させる手法、「コミュニティ共創法」を取り上げる。
<連載ラインアップ>
■第1回 斬新な着想を得るための「ランダム刺激発想法」とは?
■第2回 商品開発のプロセスに顧客を巻き込む「コミュニティ共創法」と実施のポイントは?(本稿)
■第3回 顧客の「欲しい」を見つける「バリュー・プロポジション・キャンバス」の使い方とは?
■第4回 ライバルとの比較で独自のビジネスを構想する「戦略モデルキャンバス」の使い方とは?
■第5回 「儲ける仕組み」と「コスト構造」を明らかにする「収益モデル」の使い方とは?
■第6回 新たな成長戦略の策定に活用できる「アンゾフの成長マトリクス」とは?
■第7回 経済学者H・ミンツバーグが提唱したSWOT分析の発展形とその使い方とは?
■第8回 注力すべき事業・商品・顧客が分かる「パレート分析」とは?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
コミュニティ共創法 概要
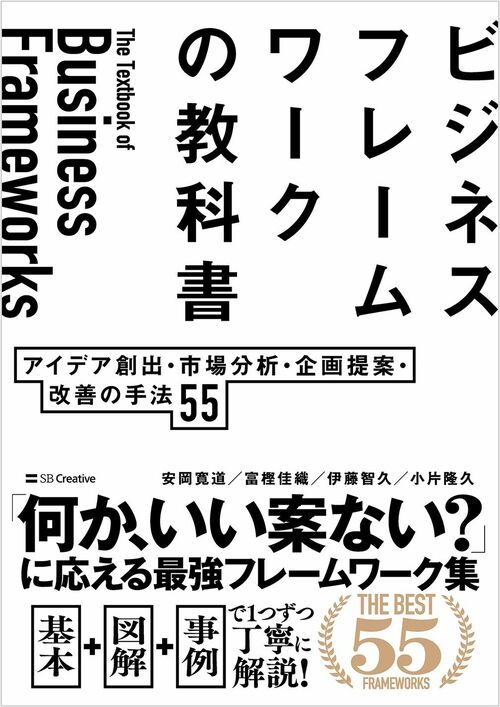 『ビジネスフレームワークの教科書』(SBクリエイティブ)
『ビジネスフレームワークの教科書』(SBクリエイティブ)
コミュニティ共創法は、顧客(ユーザー)とともに新商品や新サービスを開発する手法です。一般的な例としては、次のようなケースがあります。
- 自社のWebサイト上で顧客に商品化してほしいものを募り、それをもとにして開発担当者が検討を進める
- 商品開発の途中で、顧客に複数の案を提示して投票してもらい、意見を反映する
日本では、無印良品の商品開発が、顧客の意見を反映する共創型の開発手法の代表例としてよく取り上げられます。
インターネットが普及する以前は、企業が顧客の声を拾う主な手法は「カスタマーセンターでの電話による顧客の声の収集」でしたが、2000年以降は自社のSNSグループ(Facebookなど)や、Webサイトなどから顧客の声を収集できるようになり、商品やサービスに顧客の声を反映することが容易になりました。それに伴って、新商品の開発プロセスに顧客を巻き込む「コミュニティ共創法」が発展してきました。
「共創」という言葉は、ミシガン大学ビジネススクール教授のC・K・プラハラードが著書『価値共創の未来へ―顧客と企業のCo‐Creation』(2004年、武田ランダムハウスジャパン)の中で「顧客と一緒になって価値を生み出さなければ企業は競争に生き残れない」と説いたことからはじまっています。
「コミュニティ」という言葉は、マーケティングの巨匠フィリップ・コトラーが、デジタル時代の新しいマーケティングコンセプトを示した著書『コトラーのマーケティング4.0 スマートフォン時代の究極法則』(2017年、朝日新聞出版)の中でその重要性を示し、注目が集まっています。
デジタル時代では、顧客は、企業から一方的に発信されるメッセージだけではなく、友人やSNS上のコミュニティなどからも影響を受けるため、企業側においては、顧客に商品や企業自体のファンになってもらうために、ファン意識を醸成するコミュニティをどうのように設計するかが重要になると言われています。










