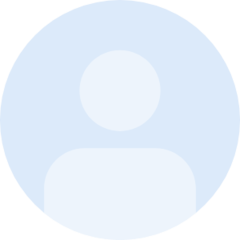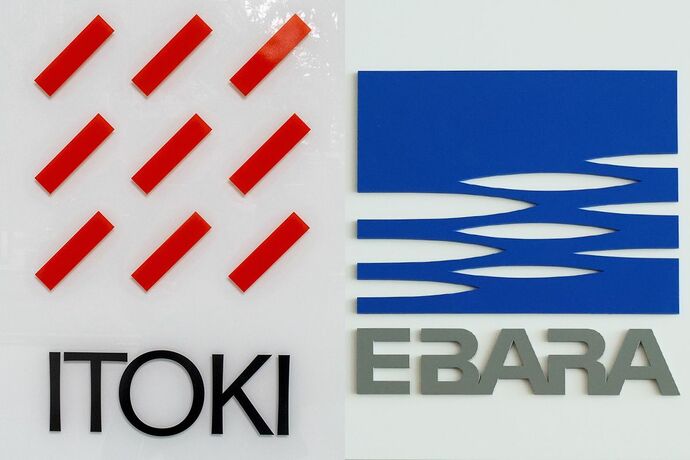(写真左から)住友電気工業 執行役員 福井雅氏、SEIビジネスクリエイツ代表取締役社長 野田太郎氏(撮影:本永創太)
(写真左から)住友電気工業 執行役員 福井雅氏、SEIビジネスクリエイツ代表取締役社長 野田太郎氏(撮影:本永創太)
ワイヤーハーネスをはじめ、世界トップシェアの製品を数多く持つ住友電気工業(以下、住友電工)。同社は2002年度、ITバブル崩壊の影響で戦後初の赤字に陥った。経営再建を託された松本正義社長(現取締役会長)は、大規模な改革を敢行し、急速な業績回復を果たす。その改革の一つに、同グループの教育・研修をグローバルで体系化した「SEI*ユニバーシティ」の創設があった。なぜ経営再建の一手として教育に目をつけたのか。それから現在まで続くSEIユニバーシティの礎はどう築かれたのか。当時、立ち上げを担った組織に在籍していた二人に話を聞いた。(第1回/全3回)
*SEI(住友電工の英語表記Sumitomo Electric Industriesの略)
必要になった「求心力」、SEIユニバーシティを立ち上げた理由
2004年、住友電工の新社長に松本氏が就任すると、程なくしてグループ内の教育・研修を体系化した企業内大学「SEIユニバーシティ」を立ち上げると社員に宣言した。
そのための組織再編も行われた。これまでグループの教育・研修を担う人材開発チームは、人事部の中にあったが、このタイミングで人材開発部として独立した。そうして当時の人材開発部長の指揮のもと、この組織がSEIユニバーシティの立ち上げを担った。
それにしてもなぜ、経営再建の一手としてSEIユニバーシティを設立することになったのか。「大きな目的の一つは、グループの求心力をグローバル全体で高めることでした」と語るのは、当時の人材開発部の一員であり、現在、住友電工のグループ子会社SEIビジネスクリエイツ代表取締役社長である野田太郎氏だ。

「1990年代以降、日本経済が沈滞する中で、住友電工ではグループの分社化を進めました。事業ごとに利益責任を持たせるのが狙いです。それにより2004年当時には、グループ会社数は全世界で200社以上となりました(現在は400社以上)。一方、この構造改革を行ったことで、各社が部分最適に陥るのではという危機感も抱いており、グループ全社の求心力や一体感を生み出す必要が出てきました。そこでSEIユニバーシティを作り、世界200社以上、約9万人の従業員(2004年当時)に、住友電工の企業理念やビジョンを伝える場、住友電工の向かう先を議論できる場を作りたいと考えたのです」
住友グループには、代々語り継がれる「住友事業精神」がある。松本氏は、こうした精神などを改めて世界中のグループ会社に伝えることで、求心力を生もうと考えた。
同じく当時の人材開発部に在籍し、現在は住友電工の執行役員を務める福井雅氏は、「松本社長は“Glorious Excellent Company” を旗印として掲げました。Gloriousの柱は住友事業精神、Excellentは企業として優れた業績を意味します。『論語と算盤』に例えるなら、優れた業績を上げるための従業員のスキルという“算盤”の教育を行うと同時に、事業精神や理念という“論語”の浸透が必要だったのです」と話す。

「それまでも年頭挨拶や社内報など、各場面で事業精神や理念は伝えられてきました。しかし、もっと印象に残る形で届ける必要があったと言えます。研修のスタイルで企業理念や経営者の思いを伝え、受講者もそれに対して思うことを話す。こうしてグループ全体が一体になる舞台を作ろうと考えました」(福井氏)
求心力を高めるだけでなく、基本的な教育の底上げという目的もあった。そこでSEIユニバーシティのコンセプトとして打ち出したのが「全員教育」だ。それまでの教育や研修は、昇進のタイミングで特定の人材が受講するものや、希望者が手を挙げて受講するものが多かったが、SEIユニバーシティはグローバル全員が受ける教育体系を構築することを目標とした。これも松本氏がこだわった点だったという。