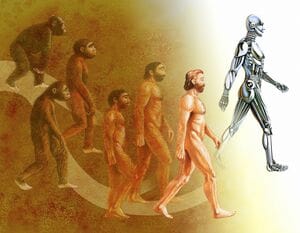予期せぬ相続発生の可能性が高まっている(写真:yoshi0511/Shutterstock.com)
予期せぬ相続発生の可能性が高まっている(写真:yoshi0511/Shutterstock.com)
結婚して家族を持たない「おひとりさま」のライフスタイルや消費行動が注目されるようになって久しい。今後急増すると見られているのが「おひとりさま高齢者」の相続問題だ。相続の現場では既に、甥(おい)や姪(めい)に当たる人物が、生前ほとんど交流のなかった「おひとりさまのおじやおば」の相続人となるケースが増えてきているという。相続で引き継ぐ対象には借金などの負債も含まれる。相続人・被相続人双方にとって望ましくない“疎遠なおじ・おば”からの相続リスクを回避するにはどうしたらいいのか。民間サービスや行政の動向を追った。
(森田 聡子:フリーライター・編集者)
遺産を「もらえる」相続ばかりではない
「叔父様が当施設で永眠されました。ついては、あなたに相続人としてお手続きをお願いします」
遠方の聞いたこともない高齢者施設から突然封書が届き、そこにはこう書いてあった。
筆者の仕事関係の40代男性が昨年、実際に体験したことだ。
男性の叔父は生涯未婚で遺体の引き取り手がなく、戸籍を調べて唯一の肉親である兄が既に亡くなっていたことから、その長男に当たる男性に連絡が行ったようだ。とはいえ、亡父と不仲でほとんど交流のなかった叔父とは、40年近く前の小学生時代に数回会ったきりだった。
消息も知らない叔父の死と相続の知らせ。それだけ聞くと、「巨額の遺産が転がり込んで人生が好転!」という映画や小説のような展開を思い浮かべる人もいるかもしれない。
しかし、現実はそう甘くはない。