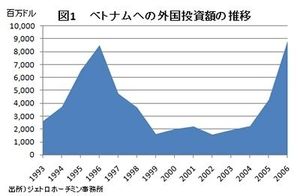インドが巨大消費市場として脚光を浴び、話題になるようになってから久しい。日系企業によるインドへの進出も盛んだが、その事業の内実は「苦しんでいます」との声が多い。
一方で、インド市場にうまく攻め込んだ企業も存在する。そうした企業と、苦戦する企業との違いはどこにあるのか。実はインド市場で活躍する企業は、「販売」にうまくメスを入れているところが多い。
孤立するインドの現場
インド社会は複雑である。そうした社会事情から現場管理が難しいという背景がある。実際に現場育成が難しいし、育たないといった声も聞かれる。しかし、筆者が数社の日系現場やローカルの2輪・2輪部品メーカーを見た限り、土台のしっかりした現場が作られていた。
しかしながら、日系企業がインドを身近に感じているかと言えば、そうでもない。現状は、「遙かなるインド」と表現できるのではないか。
実際にインドの現地生産拠点を訪れて調査してみた。適切な言葉がなかなか思い浮かばないのだが、その時の感覚をあえて表現すると、インドの現場は「孤立している」ように見える。現場は日本との距離感について、地理的な感覚以上に疎外感を感じているのではないかと感じられた。
日系企業の人によれば、「インドでのものづくりポテンシャルは高そうだ」と言う意見もある一方で、インドでにものづくりはあまり根付かないという評価もある。
「日本はインドの市場も現場もまだまだよく分かっていないんだよ」。これが現状認識として最も多い意見だろう。筆者の直感を言えば、「中国の次はインドだ」と叫ばれたものの、ことに日本の本社サイドなどは現地のことをよく分かっていないのでないか、と思える。
「孤立する現場」は、言葉を換えれば、立ちすくんでいる現場とも言える。どうも日本からの援護射撃が少ない。ここで言う援護射撃とは、現場への資源投入(ヒト、モノ、カネ)のこともあるのだが、それ以上に決定的に手薄なのは、現地生産品目をインドで販売するための仕掛け、つまり出口づくりにある。
日系エレクトロニクスメーカーの中には、インドでの現地生産が軌道に乗り切らず、タイ・インドFTA(自由貿易協定)を活用したビジネスに乗り出したケースもある。だが、それによって日系エレクトロニクスメーカーのインドでのプレゼンス向上に直結するわけではない。