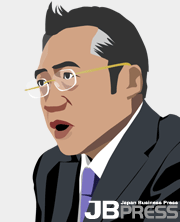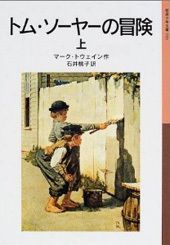「強欲」や「高レバレッジ」への国際的な批判も追い風となり、金融庁はFX業界を標的に定めた。
近く関連内閣府令を改正し、証券会社と同様に顧客証拠金の全額信託保全を義務付ける方針だ。FX業者の一部は「システム管理費がかさみ、中小業者の統廃合に追い込まれる」と抵抗し、引き受ける信託銀行の本音も「廃業の引き金を引きたくはない」。だが、金融庁は「この程度の投資をできない業者が、ハイリスク取引を提供すること自体が問題」(幹部)とけんもほろろだ。
最大数百倍に及ぶ高レバレッジ取引を危ぶみ、金融庁はFX業者が加盟する金融先物取引業協会を通じて「自主規制」を促す。「投資手法は投資家個人が選ぶもの」(幹部)としながらも、監督上の圧力を掛けながら、レバレッジ高倍率化を食い止めたい意向のようだ。
さらに、「強欲投資」の拡散を阻むため、金融庁は別の標的にも照準を合わせた。その名は、証券CFD(差金決済取引)。株式ほか多様な金融商品に借入金を使って投資し、差益を狙う「究極のレバレッジ取引」だ。個人投資家の間で「ポストFX」と目されており、流行する前に網をかける。
今国会での金融商品取引法改正では、CFDを含む店頭デリバティブについても、原則として分別管理を義務化する。FXと同様に信託保全義務を課し、高倍率化も監視することになる。
止められぬ「すべてを規制・監督」
「サブプライム後」の規制強化は、各国共通の政策課題。投資家保護を大義名分に、日本は「保護が手薄だったFX業界」(金融庁幹部)から着手した。一方、危機震源のグローバル金融界では「規制強化が実体経済の足を引っ張らないことが重要」(同)だけに、規制改革の具体化は少し先になるかもしれない。
だが、G20金融サミットが昨年11月の首脳宣言で示したように、「すべての金融市場・商品・参加者が適正に規制され、監督の対象となる」。この流れは誰にも止められない。
サブプライム問題の教訓の1つは、「どれほど精緻なリスク分散モデルを築いても、万全ではない」という点にある。そして、リスク管理に失敗した巨大金融機関の判断力は、平凡な個人投資家と変わらない。
危機発生直前の2007年、米金融界のリスク分析の大御所リチャード・ブックステーバーは警告していた。「(危機を防ぐには)金融商品を単純化し、レバレッジを減らすしかない」(『市場リスク 暴落は必然か』遠藤真美訳・日経BP社)という箴言(しんげん)は、今なお重みを増すばかりだ。
危機克服と並行して、各国の金融当局は「ポスト危機」をにらんだ規制を模索し始めた。バーゼル銀行監督委員会は3月にも銀行に対するレバレッジ規制「バーゼルII」の強化案を示す。
米AIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)の危険な巨額投資を制御できず、日本では大和生命保険が突然破綻した失敗を教訓に、保険会社の健全性基準「ソルベンシー・マージン比率」の改革機運が盛り上がる。このほか、巨大銀行やヘッジファンドをまたぐ、業態横断的なレバレッジ規制を求める声も出てきた。
果たして、高レバレッジを抑えるだけで意味があるのか。「レバレッジ批判は魔女狩りの類」(米銀幹部)といった反論もあり、詰めるべき課題は山積する。それでもオバマ米大統領は2月25日、「明確なルールが必要」「他国にも行動を促していく」と表明しており、各国当局の目指す方向は急速に固まりつつある。
重要ヒント、佐藤長官の年末発言に
FXとCFDに続く規制強化では、金融庁が米欧と足並みを揃える見通しだ。その姿を予想するうえで重要なヒントとなるのが、昨年末の金融審議会第1部会締めくくり会合。佐藤隆文長官は次のように指摘していた。
「今般の混乱で否定されたのは、短期的な利益の追求に偏った形で、高いレバレッジをかけて、不透明な金融商品を粗製乱造して取引を行ったところであろう。その意味では、今後商品の透明性が着目され、商品の標準化も進むかもしれない。また、恐らくOTC(店頭)の取引よりは、標準化された取引所での取引に重点が移る可能性もある」
ここで示唆された内容は、今後の規制改革でほぼ確実に実行に移されるはずだ。