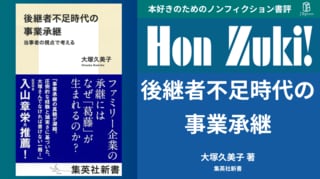8月26日、来日して記者会見するクエンティン・タランティーノ監督(左)と主演男優のレオナルド・デカプリオ(写真:アフロ)
8月26日、来日して記者会見するクエンティン・タランティーノ監督(左)と主演男優のレオナルド・デカプリオ(写真:アフロ)
クエンティン・タランティーノ監督の最新作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)が日本でも公開となった。
50年前のハリウッドを舞台に、レオナルド・ディカプリオ演じる落ち目の俳優リックと、ブラッド・ピット演じるその身代わりスタントマン「スタントダブル」を務めるクリフ、2人の架空の人物が主人公。
そして、準主役的存在のシャロン・テートをはじめ、その夫ロマン・ポランスキー、ブルース・リー、スティーヴ・マックイーン、ママス&パパスなど、多くの実在セレブが登場し、CGを好まないタランティーノらしく、大がかりなセットで当時のハリウッドの様子を再現、映画史を考慮し、細部にわたるまで配慮の行き届いた描写で楽しませてくれる。
1969年は、ハリウッドも米国社会も大きな変動のさなかにあった頃。
とりわけ、人類が初めて月に行き、ウッドストックコンサートが行われ、「シャロン・テート殺害事件」が起きた夏の様子は、50年を迎えた今夏、多くのメディアが伝えたから、新たに「歴史」として知った人も少なくないだろう。
自国の現代史の一部である米国人はもとより、タランティーノより上の世代なら日本人でも、事件、そしてその時代の様子をそれなりに知っていることだろう。
しかし、映画史にさほど詳しくなく、当時の米国社会の様子を知らない日本の若い世代からは、冗長に感じるとの声も聞かれる。
妊娠中のシャロン・テートが、友人たちとともに、ビバリーヒルズに近いシエロドライブの自宅で、チャールズ・マンソンをリーダーとするカルト集団「マンソン・ファミリー」に殺害された惨劇は、「カルト」を語るとき必ずといっていいほど取り上げられる事件である。
2人の架空の人物を登場させることで、「よく知られた歴史」とは違った「Alternative History」とでも言えるものを、タランティーノ流の「昔々ハリウッドで」の物語として語っている。
だから、「よく知られた歴史」を知らないと、様々な描写の「仕かけ」の意図が感じとりにくく、ストーリー展開の邪魔にさえなりかねない。
そこで、今回は、そんな「仕かけ」を理解するために知っておいて損はない、背景にある1960年代後半のカウンターカルチャーの時代、そして前回、前々回に続き、ハリウッドそのものの動きをみていきたいと思う。
反戦(特にベトナム戦争)、公民権運動、学生運動、ウーマンリブ、新左翼、反核、ヒッピー、フリーセックス、ドラッグ、サイケデリック・・・。
ジョン・F・ケネディ(JFK)暗殺後、米国社会は、理想を追い求める時代から、既存の権威、システムに疑問を投げかけ自由を求める「カウンターカルチャー」の時代へと変わっていった。