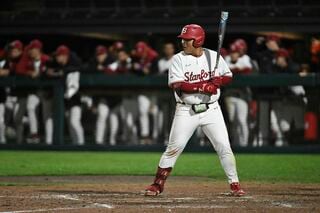2013年4月12日、アストラゼネカ社の販売する抗がん剤イレッサの最高裁判決が確定した。イレッサは2002年発売当初に、副作用の間質性肺炎による死亡例が予想外に相次いだため、原告側は薬害として提訴していた。
イレッサ裁判
国や製薬企業を相手取って8年余り続いたこの裁判は、患者側の全面敗訴で幕を閉じた(訴訟の経過の詳細については、大磯義一郎浜松医科大学教授の論考も参照して頂きたい)。
一方で、この結果に関する一連の報道では、大手新聞などの見出しで患者側の「無念の気持ち」が大きく取り上げられた。医療に対する期待を裏切られた患者側の立場からすれば、気持ちのやり場に困るのは当然だろう。紛争解決の手段としての医療裁判に限界を感じさせた事例である。
医薬品開発と利益相反
イレッサの事例は医薬品の承認販売の問題を考える格好の題材でもある。製薬企業にとって、新薬承認は業績に直結する一大事だ。イレッサの年間売上高は100億円を超えると言われており、このような有力な薬剤を開発し続けることは製薬企業にとって死活問題となる。
新薬開発の過程では、少しでも良いデータ、つまり有効性に優れ副作用は少ないという臨床試験成績を出すプレッシャーの下にある。ちょうど日本では、売り上げ増につながる都合の良い臨床試験データを捏造した疑いが持たれ、臨床試験の学術論文が撤回されたという高血圧薬バルサルタンの問題が非常に注目を集めている。
これほど極端でないにしても、アカデミアと製薬企業の不適切な関係は以前から取り沙汰されており、筆者の経験からもイレッサ開発当時の医療界では、製薬企業からの飲食接待などは頻繁に行われていた。
現在でも、アドバイザリーボード、学会のオピニオンリーダーの講演会や原稿の謝礼、研究資金提供といった名目で製薬企業からアカデミアに金銭が流れる仕組みは連綿として続いている。イレッサの開発過程においても、肺がん研究で高名な研究者たちが製薬企業と深く関わり、裁判でも証人として出席していたのは有名な話だ。
透明性を確保した産学連携は必要だが、行き過ぎると製薬企業に有利なデータだけ提示するようなバイアスがかかりやすい構造にある。
このため医薬品開発では、利益相反のない第三者による公平なデータチェックが必要となり、新薬が承認されるためには、製薬企業から提出された医薬品の実験データ、臨床試験データを規制当局が審査し、承認の可否を判断する仕組みが世界的に取られている。
医薬品の規制当局
国際的にはそれぞれの地域が独自の規制当局を有し、医薬品の承認審査を行っている。米国の Food and Drug Administration(US FDA、米国食品医薬品局)、ロンドンに拠点を置く欧州連合の European Medicines Agency(EMA、欧州医薬品庁)が世界の医薬品販売の動向を実質的に左右している2大機関だ。
そのほかの国も、カナダ、オーストラリア、中国、韓国など国民国家の枠組みでそれぞれの規制当局を設けており、日本では厚生労働省と独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)がその役割を担っている。
なお、近年では無国籍化したグローバルメガファーマが医薬品開発の趨勢を握っており、現状のような国民国家単位での医薬品規制の仕組みには早晩限界がくる可能性がある。