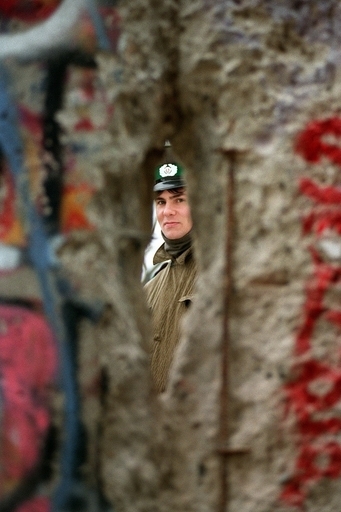このリポートの要点をかいつまんで記せば、次の通りである。
1.移行経済諸国の方が発展途上国よりも、今回の危機の影響を強く受けているが、それは国際経済への統合(貿易面、金融面、人的交流・雇用面)がより進んでいるからで、その結果、先進国経済の混乱が大きく波及した。
2.しかしながら、移行経済諸国の間でも危機の影響は一様ではなく、大きな差異がある。それは移行経済政策の違いによる。
3.今回の危機対策としては、金融機関のリストラを成功させるとともに、社会的安全網の拡充が必要である。
4.危機後の経済成長は、以前の好景気のような力強いものとはならないだろうから、回復をより確かなものとするために構造改革を進め、好ましいビジネス環境を作り出すことが求められている。
5.これまで社会主義の好ましい遺産として考えられてきたインフラ(社会資本)や労働の質の高さが、今後は経済成長のボトルネック(隘路)となる可能性が高いので、民間資本を活用したインフラ整備の充実や、教育(職業訓練・再教育を含む)の一層の拡充が必要である。
どうやら世界銀行も、体制移行プロセスが失敗だったと考えているわけでは決してなく、むしろ国際経済の統合という観点で成功したがゆえに、今回の危機が大きく影響したと見ているようだ。
では、移行経済政策の相違により発生するという差はどこにあるのだろうか。
一般的に、経済成長の原資である資本蓄積が不足している移行国が発展するためには、(a)FDI(海外直接投資)や外国融資などの形で国外から資金を持ってくるか、それとも(b)国内で限られた資金を政府が集中的に管理してそれを効率的に投下するかのいずれかが必要である。従って、そのいずれも実現できなければ、(c)低水準の成長に甘んじなければならない。
移行諸国の国際経済への統合:成長パターンと危機の深刻度の関連
実は、こうした観点から30カ国弱の移行経済諸国を見渡してみると、この3つのカテゴリーに大きく整理することができる。具体的にはハンガリーやポーランドといった中央ヨーロッパ諸国のように、ドイツやオーストリアなど近接する西欧諸国からのFDIを獲得して急速な経済発展を成功させたグループがある。このグループは先に述べた(a)の範疇に属する。
他方で、ロシアやカザフスタンのように国内の貴重な天然資源の輸出によって資金を獲得し、それを原資として国が積極的に経済開発を行おうとしているグループもある。これは(b)のカテゴリーである。