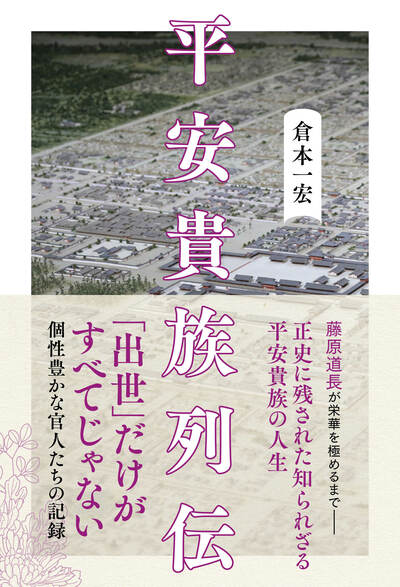越前・敦賀 撮影/倉本 一宏(以下同)
越前・敦賀 撮影/倉本 一宏(以下同)
(歴史学者・倉本 一宏)
日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。前回の連載「平安貴族列伝」では、そこから興味深い人物を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像に迫りました。この連載「摂関期官人列伝」では、多くの古記録のなかから、中下級官人や「下人」に焦点を当て、知られざる生涯を紹介します。
*前回の連載「平安貴族列伝」(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。
渤海からの公式使節「渤海史」の通訳
渤海使(ぼっかいし)の通事(つうじ/通訳)を務めた大蔵三常(おおくらのみつね)を紹介しよう。
渤海使というのは、六九八年から九二六年まで、現在の中国東北地方を領域とした渤海から日本に来朝した渤海の公式使節のことである。奈良時代の神亀(じんき)四年(七二七)から平安時代の延喜(えんぎ)十九年(九一九)まで、三三回を数える。はじめは唐(とう)・新羅(しんら)を牽制するという政治的な目的で日本に遣使してきたが、唐との関係が安定すると次第に貿易を重視する経済的な目的へと変化していった。
このため平安時代になると、渤海使の一行は商人団であるので国賓(こくひん)として接待するには及ばないとする意見も出され、次第に来航間隔や人数に制限が設けられたが、渤海使は在唐留学僧(るがくそう)の情報伝達などの口実を設けては来航を企てた。
彼らのもたらす毛皮(特に貂[てん])や唐物(からもの)は日本人に珍重され、一行は問題がなければ入京して、内蔵寮(くらりょう)管理のもとに公貿易を行ったが、年期違反などによって入京が認められない場合でも到着地付近で私貿易を行うため、朝廷から何度も禁制が出されている。
なお大使以下の幹部には漢詩文に堪能な者が多く、日本人との間に交わされた漢詩文が『経国集(けいこくしゅう)』などに散見している。また渤海使の来航に備えて能登(のと)や敦賀(つるが)に客館(きゃくかん)が設けられていた(以上、『国史大辞典』による。石井正敏氏執筆)。
この延喜十九年の渤海使は、最後のものであるが、『醍醐天皇御記(だいごてんのうぎょき)』に詳細が記録されている。以下、日付を追って見ていくことにしよう。
・十一月十八日。(『扶桑略記』による) 渤海使来着
大納言(だいなごん)藤原朝臣(道明[みちあき])が、(藤原)尹文(まさふみ)を介して、若狭守(わかさのかみ)(藤原)伊衡(これひら)の許から、渤海客徒(ぼっかいきゃくと)が来着したとのことを告げて来たことを奏上させた。
・十一月二十一日。(『扶桑略記』による) 渤海使牒状
客徒の牒状(ちょうじょう)に云ったことには、「丹生浦(にうのうら)の海中に浮いていました」と云うことだ。ところが、着岸したということは無かった。また、牒中に人数及び来着したとのことを載せているとはいっても、未だ子細の状況は記していない。蔵人(良峯)仲連(なかつら)を介して、若狭(わかさ)国の解文(げぶみ)を六条院に覧せ奉らせた。
・十一月二十五日。(『扶桑略記』による) 渤海使安置
右大臣が渤海客徒について定め行なった事〈若狭から遷して越前(えちぜん)に安置し、また入京させる事。〉を奏上した。左中弁(さちゅうべん)(藤原)邦基(くにもと)朝臣を行事(ぎょうじ)の弁とした。
十一月十八日に若狭から、渤海使が来着したことを知らせてきた。二十一日には渤海使が来着の状況を記した文書がもたらされた。朝廷では若狭国からの文書を六条院(河原院[かわらのいん])にいる宇多(うだ)法皇に覧せている。かつて宋(そう)人に謁見したことを反省しているなど(『寛平御遺誡(かんぴょうのごゆいかい)』)、外国人との接触に敏感な宇多に知らせておいた方がいいとの、醍醐天皇の判断であろう。二十五日、右大臣藤原忠平(ただひら)は、渤海使を若狭から越前に遷して安置し、また入京させることを定めた。
・十二月五日。(『扶桑略記』による) 渤海使存問
式部少丞(しきぶのしょうじょう)橘惟親(これちか)と直講依知秦広助(ちょっこうえちはたのひろすけ)を、存問渤海客使(そんもんぼっかいきゃくし)とした。阿波権掾大神有卿(あわのごんのじょうおおみわのありあき)を通事とした。渤海客饗宴(きょうえん)の日の権酒部(ごんのさかべ)の数四十人を定めた。前例では、八十人を選んで命じた。去る延喜(えんぎ)八年は、その数がすでに多く、用が無かった。そこで定めて減じさせた。
・十二月十六日。(『扶桑略記』による) 渤海使宴の舞人
内教坊別当右近少将(うこんのしょうしょう)伊衡を内教坊(ないきょうぼう)に仰せ遣わして、渤海客饗宴の日の舞人(まいびと)を撰び定めた。内教坊は、舞人二十人・舞童(まいのわらわ)十人・音声(おんじょう)二十人を調備すると仰せ定めた。去る延喜八年は、音声人三十六人であった。今回は定めて減じた。この他、威儀(いぎ)二十人は、通例によって内侍所(ないしどころ)が、女嬬(にょじゅ)たちを選ぶこととなった。
十二月五日、渤海使を存問する使と、饗宴の日に仮に酒部とする者を定めた。存問というのは、施設などの安否を問い、慰労することで、これは外交儀礼の一つである。酒部というのは、令制では宮内省所管の造酒司に属した伴部のことで、公用の酒の醸造を職掌とした者のことであるが、ここでは「権(かり)」とあるから、臨時に饗宴の日に渤海使を接待する者のことであろう。これまで八十人を選んでいたのだが、前回の接待では数が多すぎて用が無かったので、半分の四十人を定めている。渤海使の扱いが徐々に簡略になっていくのがわかる。十六日に、饗宴の日の舞人を選んでいるが、これも前回よりも減らしている。
・延喜二十年(九二〇)五月五日。(『扶桑略記』による) 渤海使入京
渤海客徒が入京する日、および蕃客(ばんきゃく)が入京する際に禁物(きんもつ)を着すことを聴(ゆる)すべきであることを定めた。滝口右馬允(たきぐちうまのじょう)藤原邦良(くによし)たちに、実際に客が京にいる間、毎日、新鮮な鹿二頭を進上すべき事を召し仰せた。
・五月七日。(『扶桑略記』による) 漢語通事
明経学生刑部高名(みょうぎょうがくしょうおさかべのたかな)が内裏に参った。漢語(かんご)の者について問わせた。高名は、あれこれを奏上した。行事所(ぎょうじしょ)は、漢語の者である大蔵三常を召すことができた。すぐにこれを蔵人所(くろうどどころ)に召した。高名を介して、申させて云ったことには、「その語を、よくするか否か」と。奏上して云ったことには、「私(三常)の唐語(とうご)は、最も広博(こうはく)でしょう」と云うことだ。勅して、公卿が定め申したことに従い、三常を通事とさせた。
さて翌年、いよいよ渤海使が入京することとなった。本稿で述べる大蔵三常も、ここで登場するのである。五月五日、醍醐は入京に際して渤海使に禁制の装束を着すことを許し、毎日、新鮮な鹿二頭を進上するよう命じている。彼らは肉食であるという認識によるものであろう。
七日、渤海使の通事を定めた。渤海はもちろん、「漢語」(中国語)を公用語としており、日本でも公文書の世界では漢文が使われている。ただし、それを正確に発音できるかどうかは、また別の問題で、優秀な通事が必要となるのである。
まあこれは、現在でも英文解釈や英作文は得意でも、英会話や聞き取りはからっきし駄目な人が多いから、これは古代から続く日本の伝統ということになろう。私も前の「国際的」な職場では、外国の大学で講演や講義をしたり、いつぞやは財務省で外国の財務官僚相手に講演させられたりしたことがあったが、その際に、「英語でいいですよ」と言われて傷付いたことがある。自分の話すことは英作文をしてそれを読み上げるだけでいいのだが、質疑応答には本当に難儀したものである。大学に入学した時の総長の談話に、「英会話は何も大学で学ばなくても町の英会話教室でも学べる」とあったり、例の職場の所長が、「話すのは通訳に任せておけばいい」とおっしゃったりした言葉を心の糧として、今日まで生きてきた次第である。
さて、渤海使の接遇を担当する行事所は、漢語が得意だという大蔵三常を推薦し、すぐにこれを蔵人所に召した。三常に、「漢語を、よくするか否か」と聞くと、奏上して云ったことには、「私(三常)の唐語は、最も広博でしょう」ということで、この三常を通事とさせたのである。こんなことまで決裁しなければならない天皇も大変だとは思うが、「漢語」ではなく「唐語」と答えた三常のコンテンポラリー(同時代的)な認識も、特筆に値する。意気盛んな若者の姿が思い浮かんでくる。なお、唐王朝はすでに九〇七年(日本でいう延喜七年)に滅亡しており、この延喜十九年当時はいわゆる五代十国の乱世であって、宋の中国統一は九七九年のことである。
自信満々の大蔵三常は、氏の名からわかるとおり、渡来系の東漢(やまとのあや)氏の一族の出身である。氏族内で中国語を話していた可能性もあるが、それも五世紀に朝鮮半島南部から渡来した人々の中国語だろうから、十世紀の中国語をどれだけ理解できたかは、いささか疑問ではある。
ともあれ、通事に抜擢された三常は、無事に、かどうかはわからないが、その役目を務めたものと思われる。八日に掌客使が定められ、十一日に渤海使が渤海王大諲譔(だいいんせん)の文書と貢物を進上し、十二日に豊楽院(ぶらくいん)で醍醐臨席の下、渤海使に宴を賜い、十五日に渤海使が別貢物を進上し、十六日に朝集堂(ちょうしゅうどう)でまた饗宴を催した。これらのいずれでも、三常は活躍していたことであろう。
 豊楽殿故地
豊楽殿故地
こうして渤海使は六月に帰国の途に就いたが、二十六日、日本に遁れ留まって帰らないのが客徒四人がいることが発覚した。朝廷は二十八日、彼らを越前国に安置することに決定した。
渤海使はこれが実質上、最後のもので、かつて唐から「海東の盛国」と評された渤海も、九二六年、新興の契丹(きったん)に破られて滅亡した。三常も、その後は史料に見えないことから、その後、さらなる官職に就いたとも思えないが、せめてその幸福を祈りたい。