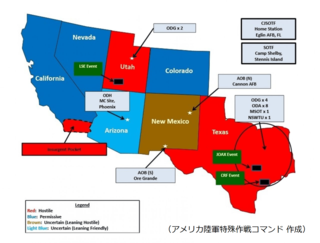半自動ライフルに取り付けられた「バンプストック」と呼ばれる装置(左)。米ソルトレークシティーの銃器販売店で(2017年10月5日撮影)。(c)AFP/Getty Images/George Frey〔AFPBB News〕
2017年10月1日、ラスベガスで58人が射殺され500人近くが負傷するという米国史上最悪の乱射事件が発生した。64歳の白人男性が、野外コンサート会場に集まった観客に向けて、近接するホテルの32階の部屋から6分間にわたって半自動火器を無差別に乱射したのである。
「銃規制」はオバマ前大統領が積極的に取り組んだテーマであったが、実現するどころか、むしろ後退さえしていたのが事件前の状況であった。だが、ラスベガスの乱射事件をきっかけに、再びさまざまな銃規制対策の提案が持ち上がっている。銃規制反対の急先鋒で、全米最大のロビー団体でもある「全米ライフル協会」(NRA)ですら、連射可能な「バンプストック」販売禁止規制という提案を出してきたほどだ。
そんな状況のなか、銃規制をめぐって、首都ワシントンで議会工作を行うロビー会社同士の激しい攻防戦を描いたハリウッド映画『女神の見えざる手』(2016年、フランス・アメリカ合作)が10月20日に日本で公開された。
濃密で濃厚に作り込まれた非常に面白い社会派サスペンスで、時間が経つのを忘れるくらいにのめり込んで見てしまった。ぜひ皆さんにも見ることをお薦めしたい。米国の銃規制問題を考えるにあたって、これ以上ないほど時宜を得た映画といってよい。
今回は、銃規制問題からみた米国社会の特質についてあらためて考えてみたい。米国がいかに異質で特殊な価値観をもった国であるか理解できるはずだ。