これが大企業による中小企業いじめの実態だ
製品をつくらせて「発注した覚えがない」と言う理不尽
2010.10.21(木)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
本日の新着

なぜAIエージェントに調査を頼むとイマイチな報告が上がってくるのか?AIのレポート精度を上げるプロンプトの特徴
【生成AI事件簿】AIエージェントが陥る4つのパターン、行動の幻覚、制約の無視、主張の幻覚、ノイズ支配を防ぐには
小林 啓倫

小売りAI革命の分水嶺:エージェント型コマース巡るグーグルと小売り大手の主導権争い
共通規格の普及と専用チップで低コスト化を加速、消費者との絆を保つ新戦略が試される
小久保 重信

「夢は何ですか?」「目標は?」と聞きすぎる社会はしんどい、髭男爵・山田ルイ53世が語る生きづらさの根本
【著者に聞く】「キラキラしてないとダメ」という圧は時には暴力に、引きこもりを美談にされる違和感
飯島 渉琉 | 髭男爵・山田ルイ53世
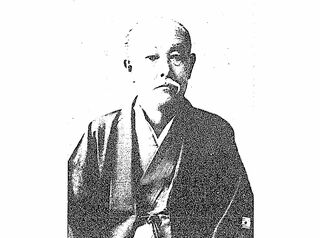
言葉を創り、思考を創る…哲学者・西周の最大の功績にして不滅の遺産とは?和製漢語の創造と分類、東アジアへの波及
幕末維新史探訪2026(5)近代日本の礎を築いた知の巨匠・西周―その生涯と和製漢語⑤
町田 明広









