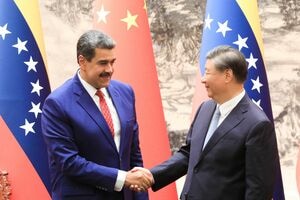中国が経済規模(GDP)で日本を抜いたのが2010年であったのが、わずか3年後の昨年末には約2倍と差を広げているという。これは、日中の成長率の差に加えて、「円安」という為替ファクターが影響しているのは明らかだ。しかしながら、このままでは日中の経済力格差は開く一方であろう。
そして中国は、GDPにおいて米国を急追しており、このままの状況が続けば、あと10年ほどで米中の逆転もあり得るとされている。
まさに中国は「台頭する新興大国」である。今年が第1次世界大戦勃発から100年ということもあって、当時のヨーロッパ情勢と現在のアジア情勢の類似性も指摘されることが多いが、歴史上の経験で言えば、「台頭する新興大国」は例外なく既存の国際秩序に異議を唱え、自国の権益を拡大するために新たな国際秩序を主張することになる。ヒトラーのドイツ、明治以降の日本がそうであった。
現在の中国が「尖閣諸島は日本が盗み取った」として東シナ海に主権の主張を強め、その上空に広大な「防空識別圏」を設定し、西太平洋で頻繁に海軍艦船の演習を実施していることや、南シナ海での主権の主張を強め、フィリピンやベトナムとの摩擦を引き起こしているのも、「現状の一方的変更」によって自らに有利な国際秩序を確立するための動きと見てよい。
日米は「うまみ」を求めて中国の大国化を支援
このような中国の横暴な外交姿勢の背景にあるのが、経済大国としての自信であるとしたら、日本の対中国政策は大きな過ちを犯していたことになる。対中「関与」政策を継続してきた米国も然りである。中国の経済発展を後押ししてきた政策は一体何だったのか。
クリントン政権時代に当たる1990年代の米国は、民主主義体制の拡大が米国をより安全にするという理念があり、89年の天安門事件によっても、中国を孤立させず、関与することで経済発展を促し、将来の民主化に期待するという考えがあった。
それよりも早い79年に日本は対中ODA(政府開発援助)を開始するが、当時の大平正芳首相は、「より豊かな中国の出現が、よりよき世界に繋がる」と中国の改革開放政策を積極的に支援していくことを表明した。日本版の対中「関与」政策の開始であった。