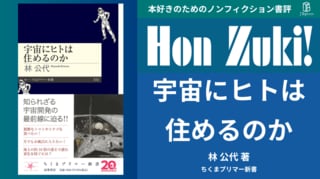2年に1度の東京モーターショー(第43回)が11月22日から12月1日までの10日間(報道関係者向け事前公開の2日間を除く)開催され、主催者発表によれば90万2800人が来場した。
リーマンショック直後の2009年(第41回)は来場者61万4400人(会期13日間)で、その前回の2007年と比較すると57%と大幅減。会場を幕張メッセから東京ビッグサイトに移した2011年(第42回)は10日間の会期で来場者84万2600人に回復していたが、そこからさらに7%を上積みした、という数字である。
この数字をもって、今回の東京モーターショーが「盛況に向かい」「日本経済の回復基調を反映して自動車市場も活性化している」と書くのは、なんとも浅薄にすぎると言わなければならない。
かつて、観客が会場にあふれて展示車を見るのにも苦労した時代もあった。もちろん今はそうした情景を見ることはない。クルマに自分自身の生活の“豊かさ”を投影し、興奮する時代がもはや過ぎ去った。それは間違いない。
しかしよく言われる「クルマ離れ」は、首都圏に居住し仕事に通っているメガメディアとマーケティングに関わる人々が自らの狭い世界観を声高に語ることで“時代の気分”を作ってしまったものであって、現実には日本の、公共交通機関が稠密なネットワークを形成しているごく一部のエリアを除いて、「クルマ離れ」どころかむしろ「クルマと共に暮らす生活」が様々に展開されている。自動車ショーは、そうやって日々暮らす人々が自分自身のごく近い明日に向けて、クルマと暮らすイメージを膨らませ、欲しいもの、あるいは良いものを考える場として機能する。
逆にその人々や社会に語りかける自動車産業側としては、まず市場を刺激すべく新しい製品像を示し、さらに自動車とその社会を考え、生み出すプロフェッショナルとして、個人個人から社会全体までがクルマとこれからどんな関係を保ってゆくのかを提案する。そしてもちろん提案する側もそれを見る側も、様々な「夢」を描く。これらが自動車ショーの役割となる。さらに言えば、こうした内容を集めた時のショーのスタイルは時代背景とともに変化してゆく。それは当然だ。
この「自動車ショーとは」という原点に戻って見わたせば、今年だけでなく最近の東京モーターショーの内容はかなり「薄い」と言わざるをえない。
東京で「ワールドプレミア」が行われていた時代
そういう意味で「東京モーターショー」が世界で最高の内容を持つショーだった時代はある。筆者自身の体験を振り返れば1985年、1987年、1989年の3回がそのピークだった。