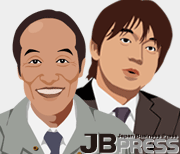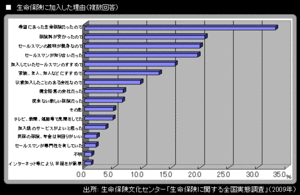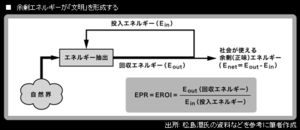なぜ生保事業に「ユニバーサルサービス」が必要なのか?
鳩山連立政権の郵政改革の趣旨は、地域社会や住民生活の拠点として機能する郵便局ネットワークの公益性・地域性に鑑み、郵便事業を永続的なユニバーサルサービスとして堅持することである。これに政府が一定の経営関与をしたとしても、1つの考え方として納得できなくはない。
しかし、そのコストを賄うために金融事業への政府関与を維持し、収益を充てるという考え方には疑問符を付けざるを得ないとの声が上がっている。
この方向性を正当化する政府の論拠は「ユニバーサルサービス」に集約される。つまり、金融事業に関してもユニバーサルサービスは「公平性の観点から求められる責務」であり、政府の関与が必要だというわけである。しかも、「国民ニーズの多様化に対応しなければならない」とのお題目の下、政府関与ゆえに制限していたはずの保険金の引受限度額や事業領域を拡大させる構図となっている。
果たして、生命保険事業にユニバーサルサービスを課す必然性があるのだろうか。
民主党は2004年に立ち上げた「郵政改革調査会」での議論をたたき台にして、「郵政改革法案」を2005年10月に国会へ提出している。その法案では、簡易保険については2007年10月に廃止し、既契約分についても複数の保険会社に分割・民営化することになっていたはずだ。
生命保険は、加入者が必ずしも頻繁に店舗を訪れる必要のあるサービスではない。営業環境は変化しつつあるが、現在でも訪問販売が主流であり、全国で25万人の営業職員、80万人の代理店募集人が全国津々浦々をカバーしている。代理店と生命保険会社の店舗を合計した営業拠点は約12万にも達する。
最近では通信販売に加え、インターネット上で契約を完結できる保険会社なども市場参入しており、消費者のアクセス機会は相当確保される。また、保障サービスという分野で見れば、JA共済などの各種共済事業者も全国の拠点を通じてサービスを提供している。
さらに、郵便局は保険販売の1つのチャネルとなっており、保険会社の提供する商品を販売することで手数料収入を得ている。郵便局へのアクセスを確保すれば、かんぽ生命に政府がわざわざ関与しなくとも、現行の郵政民営化法スキームの中でもユニバーサルサービスの実現は可能であると指摘する向きは多い。
郵便事業が真に必要なら、税金投入ではいけないのか?
生命保険文化センターが実施したアンケート調査(平成21年度生命保険に関する全国実態調査)によれば、かんぽ生命に加入した世帯のうち、その直近の加入契約について「近くに他の生命保険会社や共済がないのでかんぽ生命に加入した」という回答はゼロ。ユーザーである国民の視点からも、かんぽ生命がユニバーサルサービスを負う必要性に乏しい現実がこのアンケートから浮かび上がっている。
政府は、生命保険事業にユニバーサルサービスを課す根拠を明確に示しておらず、担当大臣らも会見や国会審議などで「国民視点で利便性の向上を」と繰り返すだけ。存在した方が便利なサービス産業など生保に限らず幾らでもあるのに、「なぜ民業圧迫を強いてまでかんぽ生命の肥大化を図るのか」と訝しがる産業界の関係者も多い。
また、「金融事業の収益で郵便事業のコストを賄うことの是非が明確になっていない」との指摘もある。「税金投入による国民負担を避ける」という考え方もあるのだろうが、郵便事業が赤字覚悟でもやらなければならない真に必要な公共サービスならば、そもそもなぜ税金投入ではいけないのかとの論理も成り立つはずだ。