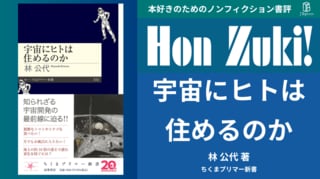ポルシェが開催したプラグインハイブリッドのテクニカルワークショップ(技術紹介イベント)に参加する機会を得たので、今回はそこで見聞したもの、特に欧州高性能車メーカー流のハイブリッド動力システムに対する考え方とクルマづくりの方向性を紹介してみたい。
 2013年7月末から欧州市場に出荷開始。日本へも年内には投入されるポルシェのプラグインハイブリッド第1作、パナメーラS E-Hybrid。スーパーチャージャーを装着したV型6気筒、エンジンとの間にモーターを組み込み8速ATと組み合わせた動力機構から後輪へ駆動軸が伸びる。車体後部の荷室下部に大容量のリチウムイオン電池を収め、そこから前部の電力制御系、さらにモーターへとオレンジ色の太い電力配線が伸びる。(画像提供:Porsche)
2013年7月末から欧州市場に出荷開始。日本へも年内には投入されるポルシェのプラグインハイブリッド第1作、パナメーラS E-Hybrid。スーパーチャージャーを装着したV型6気筒、エンジンとの間にモーターを組み込み8速ATと組み合わせた動力機構から後輪へ駆動軸が伸びる。車体後部の荷室下部に大容量のリチウムイオン電池を収め、そこから前部の電力制御系、さらにモーターへとオレンジ色の太い電力配線が伸びる。(画像提供:Porsche)拡大画像表示
すでに欧米メーカーも少なからぬハイブリッドモデルを市場に送り出している。メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、そしてポルシェ、シボレー/キャデラック、フォード・・・。そのほとんどが中大型乗用車への採用であることにも、「公的試験法における燃費チャンピオン」を追いかけてきた日本のメーカーと異なる技術論理が表れている。ハイブリッド動力化によって何パーセントかの燃費改善が期待できるのであれば、もともと燃料消費が多いクルマのほうが現実に使う中で削減できる燃料の絶対量は大きい、という考え方だ。
ポルシェもまず大型高性能SUVのカイエンにハイブリッドを投入。これは車体や走行機能要素の基本を共有するフォルクスワーゲン・トゥアレグ、アウディQ7と同じ駆動システムを組み込んだもので、エンジンとトランスミッションの間にモーターを挟み込み、エンジンとモーター両方の力を使って走ることも可能だし、モーターとエンジンの間にあるクラッチ(伝達断続機構)を切り離してモーターの力だけをトランスミッションを介して駆動輪に伝える、つまり電動車両の形で走ることも可能。トランスミッション側のクラッチを切り離せば、停車状態でエンジンでモーターを回して発電(電池を充電)することもできる、というステムである。こうした機構を、とりあえず「1モーター・2クラッチ方式」と呼ぶことにしよう。
次々に登場する「プラグインハイブリッド」モデル
ちなみに1997年登場のプリウスを始祖とするトヨタのシステムは、遊星歯車を構成する3つの歯車要素のそれぞれにエンジンとモーター、そして発電機を連結し、発電機の負荷(言い換えれば回転反力)によってエンジンとモーターの出力をどう「混合」するかを決めるという、シンプルで巧妙なメカニズムである。その反面、クルマの速度の変化と原動機の回転変動が一致せず、特にエンジンの回転はクルマが走る速度とは関係なく上がったり下がったりする。
機能としては「電気的に動作するCVT」という見方もでき、ドライバーにとって運転の基本操作の1つである「走る速度の調節」が非常に難しいシステムになっている。また、その機構の中で起こる事象を改めて観察すると、エンジンに投入した燃料のエネルギーの一部が機構の内部で失われる状況も少なくない。
1997年に、それまでのハイブリッド動力機構の概念を破る「動力混合」のメカニズムを、世界で初めて市販乗用車に導入したのが初代プリウスだった。その功績は自動車技術史に残るものだが、あれから15年を経てその弱点も明らかになり、世界の自動車技術界は次の進化、あるいは簡素化しつつハイブリッド動力化によるアドバンテージを得るためにはどんなメカニズムを、どう使うのがいいのかを考える段階に入っている。
そうした中での1つの試みとして商品化への動きが出ているのが、「プラグイン」ハイブリッドである。これも明確な定義が難しいジャンルなのだが、一応「内燃機関と電動機の2種類の原動機を持ち、自車に蓄えた電力によって電気動力だけの走行ができ(つまり純EVとしても走れて)、その電力を外部電源から充電することもできる車両」ということになるだろう。
GM(ゼネラル・モーターズ)が「電気自動車」と称している「シボレー・ボルト」も、発電および走行に用いるエンジンと変速・伝達機構を備えているので、このプラグインハイブリッドに属する。
ボルトに関しては、電気動力だけで走ることが好ましい状況は各所にあるとしても、電池に蓄えられる電力だけでは航続能力が限られてしまい、自動車として実用に供することができる使い方、ユーザーは限定されてしまう。特にアメリカの広大な国土と、自動車による中長距離移動が当たり前になっている使用環境には、浸透が期待できない。そこを液体(または気体)燃料と内燃機関でカバーしようという製品企画である。