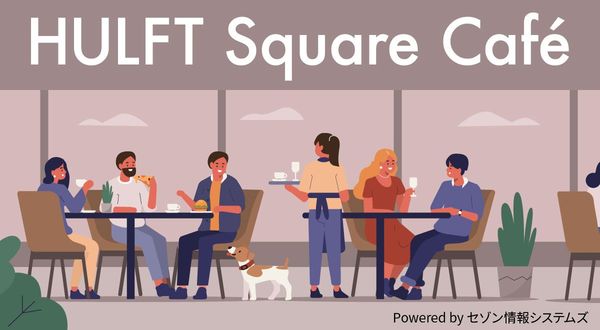本企画は、セゾン情報システムズが提供するデータ活用による新たなビジネス創造へのヒントとなるデータ活用情報サイト「HULFT Square」との共同企画となります。「HULFT Square」と連動し、JBpressでは「HULFT Square Café」と題し、実際にデータ活用を実践されている企業の経営者インタビューを特集します。
作業服市場で圧倒的なシェアを誇るワークマンだが、近年、アウトドアウエアで新たな客層を取り込んでいる。その発想転換の根底には、土屋哲雄氏(ワークマン専務取締役)が進めた「データ経営」への改革がある。ワークマンのデータ経営とは何か、データを活用することで何が見えてくるのか、土屋氏に聞く。
データ経営の目的はコミュニケーション
――2012年、土屋氏は30年以上の総合商社勤務を経て、ワークマンに入社する。そこからワークマンの改善が始まるわけだが、当初、土屋氏はワークマンの課題をどう捉えたのだろうか。
とにかく、ワークマンは作業服の市場で2位を大きく引き離し、圧倒的1位という存在。「愚直に作業服を深掘りしている、とにかく実行力の会社。上がやれということはできるまでやる、とにかくトップダウンの会社」だったという。
圧倒的なシェアを持つことは有利な半面、あまりにも競争がないという状態はある種の思考停止にもつながりかねない。トップダウンの組織においてよく見られることだと思うが、現場の従業員は自分の頭で考えなくなる。ビジネスがうまく回っているうちはそれでもいいかもしれないが、作業服市場を取り尽した後の新市場への進出が難しくなってしまう。
土屋 トップダウンなので指示待ちだったんですね。上の顔色ばかり見ている。これが一番の問題でした。それを、現場解決型というか、データを使って現場で解決する形にできないかと。われわれはデータ経営と呼んでいるんですが、これは儲けるためにやるんじゃなくてコミュニケーションのために行っています。データは平等ですから、上の人、下の人もない。持っているデータが違っているか、あるいは解釈が違っているかのどちらかしかないわけです。そこで、データで平等に議論して、現場で問題解決する。要するに現場改善型の会社にしたいという感じでした。
 株式会社ワークマン 専務取締役 土屋 哲雄 氏
株式会社ワークマン 専務取締役 土屋 哲雄 氏
――それまでのワークマンではデータの活用がされていなかったという。そもそも、データ自体がなかった。売り上げ等の金額データはあったが、店舗在庫の数量データは持っていなかった。決算にしても、棚卸しをして、仕入れ数と販売数を足し引きすれば必要な数字は出る。「余計なことをしない会社なので、数量データ自体がなかった」のだ。
いわゆるブルーオーシャンで、競争がないことでデータを見なくてもよかったわけだが、顧客の満足度となると話は別だ。ワークマンの標準店舗は100坪。マスター登録されている製品の数は5000、そのうち店舗に置けるのは2000アイテム程度になる。
これはどういうことかというと、作業服といっても建設から工業、農業、林業、漁業、サービス業と多岐にわたるわけで、地域によって求められる品揃えは異なる。例えば、林業に従事する人にとってスパイクのついた長靴は重要なアイテムで、そのため、産業統計的に林業の盛んな地域ではスパイクシューズを置く。
しかし、スパイクシューズは山があって山菜が採れるところでも相当売れるし、農家にしても作業服を着て農業をする人と、ジャージとか普段着でカジュアルに作業をしてしまう人と2種類ある。つまり、店舗に求められる品揃えはその店舗に行ってみないと分からない。
土屋 品揃えをどうするかというのはそれぞれの店舗で違うんですよ。現場で、本部のスーパーバイザー(注・経営指導員)がデータ活用マインドを持って最適な品揃えを加盟店に提案する。それによってお客さまの満足度が一番高まることになるわけです。 少し前に高知県の四万十市に行ってきましたが、そこはカツオの一本釣りが盛んな地域が近い。川で有名だから、川沿いだと思ったら、南の方の土佐清水や黒潮町が商圏なんですね。となると、水産用のものがなかったら、例えば、漁業用の胴までくるツナギのような長靴があるんですが、それがないと品揃えとして全然、駄目。漁業関係者がその店に行くとがっかりしちゃうことになるんです。
このように品揃えのポイントが個店ごとに違うということは、全スーパーバイザーがデータを使えなきゃ、最適な品揃えはできないということになるわけです。
――要するに、ワークマンはデータをもとに品揃えを変えていくことが顧客満足度を高める一番の手段であると舵を切ったのだ。もちろん、そこには、「データとは共通言語」であり、「みんながデータで議論し、会社の方針を決めていくためのもの」だという信念があった。