2014年秋、福島県相馬地区では250ヘクタールの田んぼから約1,300トンの玄米を収穫した。福島県浜通りに位置する相馬市は2011年3月の東日本大震災で大きな津波被害を受け、約1,000ヘクタールの水田が浸水した。中でも、岩子地区は被害の大きい激甚被災地域だった。震災直後、田んぼには津波によって運ばれてきた大量の瓦礫と、5~10センチの厚さの土砂が堆積し、「稲作の再開にはいったいどれほどの年月がかかるのか」と誰もが絶望した農地が、見事に蘇ったのだ。
 2011年5月の岩子地区
2011年5月の岩子地区
農作物にとって塩分は大敵だ。津波被害を受けた農地は、単に瓦礫を撤去するだけでなく、海の水がもたらした塩分を取り除かなければ農業復興できない―というのが、農業関係者にとっての常識だった。相馬市では、津波によって運ばれた土砂を撤去せず、敢えて、畑や田んぼの元の土壌に混ぜ込むという独自の「そうま方式」を採用した。土砂の撤去・廃棄に無駄な労力・予算をかけず、効率的な農業再生の手法として注目を浴びている。相馬市やコメ農家の「頼れるアドバイザー」として、「そうま方式」を編み出したのが東京農業大学の「東日本支援プロジェクト」だ。
日本を代表する農学系総合大学として農業界に人材を輩出してきた東京農大は、創立当初から、理論の実践に重きを置いた実学主義を教育理念としてきた。「蓄積してきた知識と技術を震災復興に役立てることこそが、我々の使命だ」という強い決意のもとスタートしたプロジェクトは見事に実を結びつつある。
津波がもたらしたのは養分豊富な土だった
東京農大の「東日本支援プロジェクト」の一団が初めて、相馬市を訪れたのは2011年5月のゴールデンウィークだった。震災から2カ月近く経っていたものの、津波に襲われた農地はほとんど手つかずのまま放置され、田畑は瓦礫と土砂で埋め尽くされていた。「果たして農業復興は可能なのか」、農業理論のプロたちですら無力感に襲われる光景だった。しかし、土壌肥料学を専門とする応用生物科学部の後藤逸男教授は、津波土砂を手にとってみた瞬間、「これは良い土だ」と直感したという。
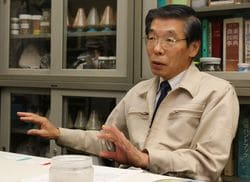 東京農業大学 応用生物科学部 後藤 逸男 氏
東京農業大学 応用生物科学部 後藤 逸男 氏
「台風などによる高波は海水の表面が陸地に押し寄せるだけだが、海水全体が動く津波が運んでくる土砂は、長年に渡って海底に貯まり続けた養分が混ざり込んでいて、素材自体は決して悪いものではない」のだ。実際に、研究室に戻って堆積土砂を分析してみると、カリウムやマグネシウムなど、本来、肥料として使われる成分が豊富に含まれており、作物栽培に適さない成分はナトリウム(塩分)だけだった。
当時、農林水産省が津波被災地向けに策定した「除塩マニュアル」では、ナトリウムを多く含む堆積土砂を取り除き、さらに、ナトリウムを吸収した土壌に石灰(カルシウム)を加えて、除塩することを推奨していた。しかし、後藤教授は「田畑一面に10センチ近く溜まった土砂はとてつもない重さと体積がある。取り除くのも大変だし、被災地にとっては処分場所の確保も頭の痛い問題。
津波は甚大な被害をもたらしたが、豊富な養分を含む土は、貴重な置き土産でもあり、これを活かさない手はない」と考えたのだ。長年、土壌改良に取り組んできた後藤教授にとって「塩分なんてちっとも怖くない。雨水で洗い流せば、除塩は簡単にできる」という確信があった。
重機がなくても除塩はできる!
後藤教授が最初に復興に携わったのは、相馬市の特産品の1つであるイチゴを生産する農家だった。丁度、首都圏などから駆けつけたボランティアが、被害を受けたイチゴのハウスから土砂を運び出す作業を予定していたが、後藤教授は農家と話し合い「ボランティアに依頼する作業は、土砂の運び出しではなく、ハウスの被覆材であるビニールの撤去に変更しましょう」と提案した。
「私の言う通りにすれば、塩分なんてすぐに流せますよ」、後藤教授が自信を持って伝えると、農家は安心してその後の対策を委ねてくれたという。実は、「塩分を洗い流す」方法は至って簡単なのだ。ビニールをはがし、土砂を雨ざらしの状態にしておくだけ。梅雨入りのシーズンだったため、1カ月もあれば、大半の塩分を雨が洗い流してくれるはずで、わざわざ重機を入れて土砂を運び出す必要はないのだ。
6月中に除塩はほぼ完了し、その後、製鉄所の製鋼工程で副産物としてできる転炉スラグを土壌酸性改良資材として施して塩分を取り除き、震災から半年足らずの8月には被災後最初の緑肥作物(ソルゴー)の種まきにこぎ着けることができた。その後、翌年2012年9月にはイチゴの苗を定植し、12月には収穫が始まった。甚大な津波被害を受けたイチゴ産地では最初の「復興」であった。
 イチゴハウスでの転炉スラグの施用
イチゴハウスでの転炉スラグの施用
後藤教授は「イチゴは最も塩分に弱い農作物の1つ。イチゴ栽培が再開できるなら、どんな作物だって、この方式を応用できる」と手応えを感じたそうだ。
 復興したイチゴハウス
復興したイチゴハウス
たった1軒の農家からの稲作再開
岩子地区の稲作農家から、東京農大の復興支援チーム宛に相談の電話がかかってきたのは、ソルゴーが順調に生育した2011年の9月だった。現地を訪れると、瓦礫は全て撤去されていた。「ここまでくれば、我々の出番だ!」―早速、2012年からの稲作再開を目指して作業に取りかかることにした。
津波土砂が堆積した一面土色の光景の中に、1カ所だけ青々と雑草が伸びている場所があった。瓦礫の撤去のために入った重機の轍の跡で、津波土砂ともとの田んぼの土壌がまじりあっていたのだ。後藤教授は「堆積土砂を取り除く必要はありません。むしろ、混ぜた方が早く除塩ができ、雑草が生えてくるのが一目瞭然でしょう」と説明すると、農家はすぐに「そうま方式(=東京農大方式)」での稲作を再開する案に納得したという。
 雑草が伸びていた轍の跡
雑草が伸びていた轍の跡
田んぼの土を雨ざらしにすることで、2012年の正月過ぎには塩分はほとんど抜けた。その後、「転炉スラグ」を施し、田植えの準備は完了した。
 転炉スラグを施用
転炉スラグを施用
ただ、震災の翌年に稲作を再開したのは、岩子地区のコメ農家約30軒のうち、たった1軒。耕作面積は1.7ヘクタール、田んぼ3枚分だった。
農家をその気にさせるのも我々の仕事
津波被害で荒れ果てた田んぼを前に、多くの農家が営農意欲を失っていた。東京農大が旗を振ってみたところで、「塩分を含んだ土で稲が育つはずなどない」と冷ややかな空気が支配的だったという。しかし、たった1軒の農家がスタートしたほんの一区画の田んぼの稲がすくすくと育ってくると、地域の人には日常生活の中で、嫌でも田んぼの様子が目に入ってしまう。最初は無関心を装っていた人たちが、やがては田んぼの前で足を止め、稲の生長を見守るように変わっていったそうだ。
稲穂が頭を垂れ、田んぼが黄金色に輝き始めると、周囲の農家の目の色が変わってきた。「最初はたった1軒の小さなスタートで十分でした。長年、稲作に携わってきた農家が、田んぼが蘇る様子をみて、心が動かないはずがありません。実践を通じて農家をその気にさせるのも、我々の仕事なのです」と後藤教授は言う。
2012年に収穫できたのはわずか10トンだったが、「そうま復興米」と名付けられ、相馬農業復興の象徴となった。
 そうま復興米
そうま復興米
津波土砂が放射能汚染から稲を守った
実は、相馬市にも原発事故後に放射性セシウムが降っていたのだが、「そうま方式(=東京農大方式)」では、津波土砂を取り除かず、田畑の土壌に混ぜ込んでいるため、塩害以上に、農作物の放射能汚染を懸念する声があった。しかし、この問題も、結果的には津波の土砂に救われたのだ。
「セシウムは、肥料として施されるカリウムと大きさ、形がそっくりで双子の兄弟のような存在」だという。土壌の養分が不足していると、作物はセシウムをカリウムと間違えて吸収してしまうのだが、カリウムが十分にあれば、当然、養分となるカリウムの方を吸収しようとする。海底に蓄積されていたカリウムを豊富に含む津波土砂を混ぜ込むことで、放射性セシウムの吸収を抑制することができたのだ。
「そうま復興米」は、福島県による全袋検査をパスし、さらに、東京農大内でのゲルマニウム半導体検出器を使った厳密な検査でも放射性セシウム不検出が確認され、安全・安心なコメとしてお墨付きを得た。
除塩も、放射能汚染も心配ないとこれが分かると、稲作再開に意欲を示す農家がいっきに増えた。震災から2年目の2013年には「そうま方式(=東京農大方式)」で稲作に取り組む田んぼが約30倍の50ヘクタールとなり、さらに2014年には200ヘクタールを追加し合計250ヘクタールとなった。来年は「そうま方式(=東京農大方式)」の水田が500ヘクタールにまで拡大する予定だ。
 「そうま方式(=東京農大方式)」
「そうま方式(=東京農大方式)」で蘇る田んぼ
東京農大の実学精神が生きる
後藤教授は「これは研究ではなく、純粋な支援だというのが私の基本的なスタンスです」と言い切る。「東京農大の復興支援予算は公的資金を受けていない独自資金で、実は他大学と比べると数分の一といった規模。でも、実際にはお金なんて、そんなに必要ないのです。土壌肥料学の分野で約40年にわたって培ってきた知識と技術を、最も必要とされるところで応用したことによって、津波で被災した農地が確実に復興しつつある。研究で積み重ねてきた知識と技術をここで提供することこそ東京農大の使命だ。東京農大がやらずして、誰がやるのだ。」
東京農大が大切にしてきた実学精神が、相馬市の農業復興に希望の道を拓いたと言っても過言ではないだろう。
<取材後記>
後藤教授は約26年前、つながりのある農家に「土や肥料のことを一緒に勉強しましょう」と声を掛け、「全国土の会」を発足させた。当初わずか30人でスタートした会だが、現在では全国600軒の農家が所属している。「東京農大の中でも、私は、特に、現場を重視し、農家の人とのつながりを大切にしてきた」と胸を張る。
被災地に入り、農水省が提唱する除塩方式とは異なるやり方を推進することができたのは、大学での研究や「全国土の会」を通じた農家との付き合いで、農家を納得させるための「ツボ」が分かっていたからだという。
即戦力になる新入社員が求められる風潮の中、多くの大学が「実学主義」を掲げるが、東京農大の実学主義は年季が違う。農家と直結した研究を通じて、日頃から農家と一緒に田畑に入っている学生は、肥料、種苗業界から引く手あまただそうだ。実学精神によって、高いコミュニケーション力を身につけた学生には、社会に出ても活躍の場が広がっているようだ。
