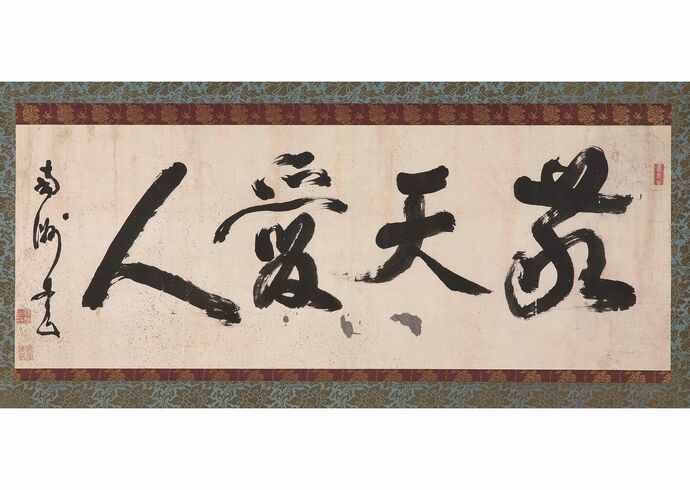yucelyilmaz/Shutterstock.com
yucelyilmaz/Shutterstock.com
人類史において、新たなテクノロジーの登場が人々の生活を大きく様変わりさせた例は枚挙にいとまがない。しかし「発明(インベンション)」と「イノベーション」は、必ずしも輝かしい成功ばかりではなかった。本連載では『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』(バ-ツラフ・シュミル著、栗木さつき訳/河出書房新社)から、内容の一部を抜粋・再編集。技術革新史研究の世界的権威である著者が、失敗の歴史から得られる教訓や未来へのビジョンを語る。
第3回では、「火星への移住」や「機械と人間の脳の接続」といった妄想に近い発明がなぜまことしやかに語られるのか、その背景にある現代社会の問題点について指摘する。
<連載ラインアップ>
■第1回 技術開発の“後発組”中国は、なぜ巨大イノベーションの波を起こすことができたのか?
■第2回 イーロン・マスクが提唱する高速輸送システム「ハイパーループ・アルファ」は、本当に実現可能なのか?
■第3回 「火星地球化計画」「脳とAIの融合」などの“おとぎ話”が、なぜ大真面目に取り上げられるのか(本稿)
■第4回 自転車、電磁波、電気システム…現代文明の基盤を築いた“空前絶後の10年間”、世界を変えた1880年代とは?
※公開予定日は変更になる可能性がございます。この機会にフォロー機能をご利用ください。
<著者フォロー機能のご案内>
●無料会員に登録すれば、本記事の下部にある著者プロフィール欄から著者をフォローできます。
●フォローした著者の記事は、マイページから簡単に確認できるようになります。
●会員登録(無料)はこちらから
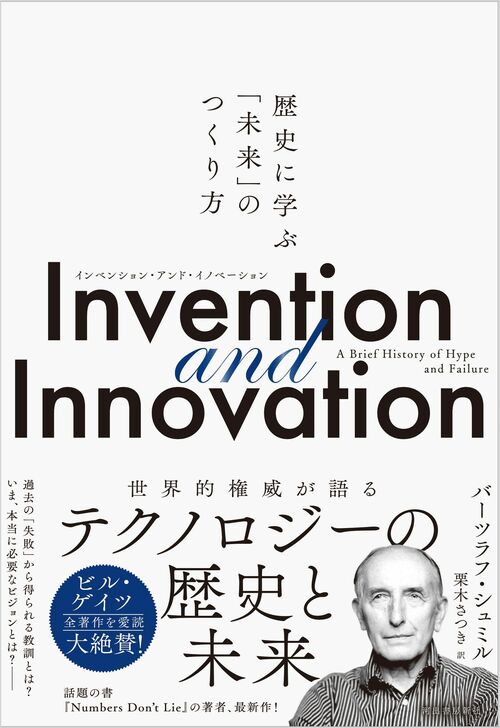 『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』(河出書房新社)
『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』(河出書房新社)
2017年、次のような予想が発表された。2022年には火星植民地化を目的とした最初の飛行がおこなわれ、その後すぐに火星を「テラフォーミング」する(大気をつくりだして居住可能な世界にする)準備をととのえ、やがては人類による大規模な植民地化が進むだろう、と。
SFの設定なら、これは古くからあるネタで、独創性のかけらもない寓話である。実際、多くの作家がこの設定をとりあげてきた。なかでも、1950年に『火星年代記』を発表した作家のレイ・ブラッドベリほど、想像力豊かに表現した作家はいない。
とはいえ、火星の植民地化は実際の科学技術の進歩の予測や説明としては、完全におとぎ話である。ところが、長年、メディアが大真面目に繰り返し報じてきたせいで、妄想にすぎない火星地球化計画がスケジュールどおりに進行しているかのような印象を与えているのだ。
さかんにもちあげられているこうした発明の規模は大小さまざまで(火星地球化から神経回路の再編まで)、サイズの小さいほうの代表例が、機械と人間の脳をつなげる「ブレイン・コンピュータ・インターフェース」(BCI)だ。
BCIはこの20年ほどで研究が進んできた技術で、特定の神経細胞(ニューロン)をターゲットにして、脳のなかに直接、小型の電子装置を埋め込み、脳とコンピュータなどとのインターフェースをとる(頭部やその周辺をいっさい傷つけずにセンサーを装着する非侵襲式の方法では、侵襲式ほど正確に脳の信号を読み取ることができない)ため、倫理的にも身体的にもさまざまな危険や不具合がともなうのは目に見えている。
しかし、BCIの進歩に関するメディアの報道を読むかぎり、そうした事実はいっさい伝わってこない。
これは私個人が感じた印象ではなく、2010年から2017年にかけて発表されたBCIに関する4000件近いニュース報道を詳細に検証した結果、得た結論である。その評決は明確だ。
メディアは過剰に好意的な報道をしただけではなく、その大半がBCIの可能性についてとんでもなく誇張して表現する非現実的な推測だった(「聖書の奇跡が実現する」、「将来の活用法は無限大」)。
それだけではなく、すべてのニュース報道の4分の1が、実現する見込みがきわめて低い極端な主張で占められていた(「ブラジルの東海岸の砂浜に寝そべったまま、火星の地表を移動するロボットを動かす」から「数十年後には不死が実現する」といったものまで)。かたや、こうした技術とは切っても切れないリスクや倫理上の問題についてはいっさい触れられていない。